| ひとりごちるゆんず 2007年4月 |
読者、貴様、見ているなッ!!
てなわけで、待望のアニメ映画化の『ジョジョの奇妙な冒険 ファントム・ブラッド』を今日は観て参りました。しかしさ、昨日観た『蟲師』もそうだけど、原作マンガを読んでからだと、どうもその違いの部分を否定的にチェックしてしまいがちですなぁ。マンガと映画とは違う媒体なんだから、表現が違うのは当たり前なのに。けど、『ジョジョの……』の方はなるだけ原作マンガに近づけようって意志が感じられたね。アニメだし。
けどさ、だったら下手に部分的に自己主張なんかしないで欲しいんだが。ヒロインのエリナの造型なんかどうよ。原作の立体的な顔立ちなんて全く無視して、かなり現代的な、萌え寄りな平面顔に変えさせられてたぞ。キャラ造型は監督自身がしたそうだから、そこらは全部監督の責任ね。んでその割には男のキャラたちの造型は原作に忠実だったりするんだこれが。ディオの目バリとか、ジョナサンの鍛え上げられたイワオのような体とか。そこらのバランスが取れてなくてなぁ。
バランスが取れてないといえば、話、カットしすぎ。たったマンガ5巻ぶんを映画にするのにここまで切らなきゃなんないのかってくらい切られまくってた。あれで90分に収めるくらいなら、原作にあったエピソードをもっと盛り込んで長くしてもよかった。おいら的には2時間超でもよかった。切り裂きジャックのくだりは多少端折ってもいいとして、ブラフォード、タルカスとの名勝負が、ザコゾンビとの戦いといっしょくたにされてしまったのが悲しかった。
確かにあれは、英国史にそんなに詳しくない一般の日本人にとっては解説が必要で(もちろんおいらも原作マンガを読む上で解説を必要とした)、マンガと違って、映画で戦闘場面でいきなりナレーションなんかやられたら、流れが止まっちゃって客がドン引きするのは目に見えてるんだけど、そこは映像のプロの腕ってやつで見事にどうにかしてほしかった。「LUCK → PLUCK」のくだりなんか男泣き場面なんだぞ。「姉ちゃん、明日って今さ!」もなくなってたし。
あと気になった省略が、スピードワゴンがもろにカットされちゃって、ひとコマたりとも出演しなかったってとこ。確かに今回のジョジョ第1部だと大した役割じゃないんだけど、この作品、おもいっきし次につなげる終わり方だったよね。続編製作はもちろんジョジョ好きとして大歓迎なんだけど、ここから先は、スピードワゴンさんがいないと話が展開しないんですが。脚本家さんをはじめとするプロットに関わったスタッフさんがた、そこらへん原作を続編、続々編にあたる部分までちゃんとチェックしたんすかね。
第2部でジョセフは誰を助けにメキシコに行くんだよ。第3部でジョースター一行の旅を支援するのはどこの財団なんだよ。このまんまじゃ話ができないぞ。どうするつもりなんだよ一体。たぶん来てた客はほとんどが原作を読んだ人たちだと思う(顧客ターゲットそこだけだし)。みんなそのことを心配しながら劇場を後にしたと思うぞ。
で、この暴挙とも言える原作カットの嵐なんだけど、仕手側の弱気な態度がそこに垣間見えてしまうんだが。上映時間が短ければ、製作コストもそんなにかからない。アニメは脚本の最終稿が出来た時点でそれ以降の変更がほとんど効かないから、90分の脚本と絵コンテを書けばきっちり90分に収まってしまう。コスト計算が楽なわけだ。で、90分という短い尺に収めることは脚本段階で決定してたってことになる。まずここで製作コストを低く抑えようという意図が見える。
そして、全国同時公開じゃなく順次公開の形を取った。これは公開用フィルムの本数を減らすのに役立つ。フィルム製作費は1本の映画で数十万かかるらしいから、ここでもあまりコストをかけないよう努力してる姿が見える(もちろん尺が短ければそれだけ安く上がるし)。実際、東京よりかなり遅れて公開された今日の映写では、フィルムがいささか汚れ気味だった。きっといろんなところを巡業してきたやつなんだろーなぁ。
この弱気の原因は、顧客ターゲット層の薄さにある。ジョジョの原作を少年ジャンプか単行本で読んで、ジョジョ好きになった連中。これだけ。ジョジョ好きは全国にいるけど、かなりまばらにしかいないと踏んだのだと思う。確かに、OVA 化やアーケードゲーム化はされてるものの、TV アニメにもドラマにもなっていないソースをいきなり劇場用映画化ってのはリスクが大きいように思える。実写にして出来ないこともないだろうけど、見栄えをかなり原作に忠実に再現できる上にコスト(特に VFX)がかからないアニメの方が安全っぽい。
しかし、アニメにするってことは、観客は見栄えばかりじゃなく、中身も原作マンガに限りなく忠実であることを求めるものなのだよね。話を勝手にカットされたりすると不機嫌になりがちなものなのだよね。そこらへんがジレンマなわけだ。しかもジョジョのファンってのはコアーなやつが多い。いちいち「そこにシビレる憧れるゥ!」なやつが多い(mixi の『ジョジョの奇妙なコミュニティ』はいつもお互いにネタのぶつけ合いで「震えるぞハート! 燃え尽きるほどヒート!!」なことになってるw)。それは原作の持つ不思議な魔力に魅せられたからなわけ。
幸いというか、第1部じゃまだ原作者、荒木飛呂彦(←おおっ、一発で変換できた!! SCIM + Anthy すげぇ!!)独自の魅力は全開されてないから、普通のアニメ製作の手法が多用できたと思うけど、それでも「無理な短尺かつ順次公開」ってところから、やっぱし仕手側がかなり弱気だったことが伺える。ここんとこ、仕手側にはもうひと越えして欲しかった。順次公開は我慢するとして、コアーな観客が映画と一体になれる見せ場は、できれば全部網羅して欲しかった。例えば、スピードワゴンさえ出てれば名セリフ「スピードワゴンはクールに去るぜ」が聞けたはず。だったらその前のエリナの献身的な看護の様子と同時に、彼女の心の強さが、年を経ても、あの辛い経験を経ても変わっていないことも見せられたはず。
そういう、仕手側の弱気な判断でケチ臭い仕上りになってしまったのが実に惜しかった。実際この映画は、ジョジョ好きの間ではあんまし評判がよろしくない。企画段階でもっと強気で押して大作路線で押してれば、原作により忠実にするだけで観客(ジョジョ好き)の評価もぐんと上がり、リピーターがジョジョ初心者を連れてネズミ算的に観客を増やしていくはずだった。そして、次回以降への望みもより強くつなげたはずだった(前述のように、スピードワゴン抜きでの続編は考えにくいけど)。全ては、製作者のジョジョ好きのコアー度の読み違いからこうなってしまったのだった。
同じく週刊少年ジャンプ出身で大成功を収めた『デスノート』2部作に比べて、こっちのシリーズ(になるかどうか知らないけど)はずいぶんと水を開けられてしまった。本当に残念でしょうがない。要するに、製作者たちに足りなかったもの、それは覚悟ッ!! 予算など気にせず、
の覚悟で製作して欲しかった。そして、ジョジョ好きな連中がいかにアツいのかをきちんと認識してから製作して欲しかった。
アニメ作品だけど、子供客は一人もいないんでやんの。PG-12 がかかってたってこともあったけど、おいらは確信したね。そこにいた観客は全員JOJOヲタだったということをッ!! おいら前から2列目で観たんだけど、上映が終わってなにげに振り返ったら、みんなそういう目つきしてたよw なぜか全員、1人で来た観客ばっかしだったよ。ふふふ、分かってるって。「スタンド使い同士は引かれ合う」。そう、その日そのとき劇場に居合わせた者たちは、運命によって引かれ合ったはずなのだよ。女性客も何人かいたなぁ。
しかし、何かにつけてシャイな青森県人のスタンド使いたちは、上映終了後に一言も会話を交わすこともなく、三々五々それぞれ勝手に帰っていったのであった。次回作『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』のとき、また会おう! やるかどうかはなはだ疑問だけど。
ディオがダニー(ジョジョが飼ってる犬)を蹴ったとき、観客たちはみんな心の中で叫んだはずだ。「何をするだァーー!!」(←JOJOヲタの間で超有名な誤植)
さらに、ディオとエリナのキスシーンじゃ「ズキュゥゥゥゥン」、ツェペリがカエルを殺さずに岩を砕くときは「メメタァ」(多用される「ゴゴゴゴゴ」や「ドドドドド」に続いて JOJO の原作で有名な擬音。1回しか使われていないことを考えると、そのインパクトがいかに強烈だったかが分かる。その次に有名なのが、ホル・ホースのスタンド「エンペラー」が出現するときの「メギャン」。その他、「ドッギャァァン」「チュミミ〜ン」「ザパラッ」などの名擬音が、JOJO の原作シリーズには綺羅星の如くちりばめられている)とみんなつぶやいたに違いない。とりあえずおいらはつぶやいた。歌舞伎の観客の掛け声みたいに、大きな声で言えばよかったかなぁ (^_^;)
すんません、昨日のログをいろいろ修正したり内容を充実させたりしてるうちに、時間切れになっちまいました。どうも JOJO 話になるとアツくなってしまうなぁ (^^;)
今日は燃料電池とか水素燃料とかバイオエタノールとかのハードな話で行こうと思ってたんだけど、眠くて眠くてしかたないんで、このへんでドロンさせていただきやす。おやすみなさいませ〜。
なんでまた FreeBSD ってのは、アプリの管理に関しては何ごとも大ごとになっちまうんかねぇ。
Firefox は、FreeBSD 用も用意されてるブラウザなわけだ。特にタブ機能の充実が売りなわけだこのブラウザは。タブのドラッグドロップでの入れ換えなんつう、いっぺん使ったら手放せないお便利機能は、今のとこ他の無料ブラウザにはできない芸当なわけだ(タブ機能さえない IE なんて論外)。ということで、最近じゃ KDE(Unix 系の GUI のひとつ)に標準装備のファイル&ウェブブラウザの Konqueror よりもっぱら Firefox ばっかり使ってる。
で、その売りのはずのタブのドラッグドロップでの入れ換えをしたら GUI 全体がフリーズしてやんの。Mac から ssh でリモートログインして Firefox を強制終了して亊無きを得たけど、どうも前から、FreeBSD 版の Firefox はこの機能の動作が危なっかしかった。だからアップグレードしようと思ったわけ。
コマンド portupgrade -n アップグレードするアプリの名前 で調べたら、微妙に新しいバージョンが確かにある。この新しいのにとっとと入れ換えようと思いますわな。で、コマンド portupgrade -PR アップグレードするアプリの名前 とやると、ウェブ上からコンパイル済みバイナリを探して拾ってきてサクッとインストールしてくれるはずだった。本編の入れ替え前に行われる依存プログラムの入れ換えでも、その要領でサクッといくはずだった。
そのアップデートしなきゃなんない依存プログラムがけっこう多いんですが。なんでこんな微妙な本編アップデートでここまで他の奴らも新調しなきゃなんないわけ? しかもバイナリが見つからなくて、結局 ports を使ってソースコードを拾ってきて自力でコンパイルしてからインストールだもんなぁ。
そんなわけで、いまだに Firefox 本編のアップグレードにたどり着けないまま、portupgrade の自動操縦に任せて今日はもう寝るです。つうか Mac だと同じ Firefox でも、アップデート作業自体が自動だわ一瞬で終わるわで、同じ FreeBSD 系列なのにずいぶん違う。アプリ管理に関するラクさ加減、ここらで有償 OS と無償 OS との差が出るねぇ。つうか、FreeBSD が Linux に比べてもいまいち普及できないでいるのは、PR 不足もあるだろうけど、こういう面倒さも原因になってるんじゃないかと。これじゃあ PR もしづらいわなぁ。
このログのチェック用に、久しぶりに Konqueror をウェブブラウザとして使ったわ。やっぱタブ機能&文字検索機能がより進化してる Firefox の方がいい〜。
読破。『なるほどナットク 燃料電池がわかる本』。いや、燃料電池のタイプ(代表的なやつだけで4種類ある)別の作動原理やなんかは1回読んだだけじゃ『なるほどナットク』なんて生易しいもんじゃなかったぞ。かといって何回も読み返す根性もなし。しかもこれ、何年か前に買って放置してたやつを、ようやく今頃読んだぐらいにして。発行は2001年。てことで、日進月歩の燃料電池技術はこの6年のブランクの間にかなり進んだと思われるんだけど、まぁ基本的な部分を理解するって意味で役に立ったな。
で、その本で得た知識の受け売りになっちゃうけど、一口に燃料電池といっても、最終的な燃料が水素だってことが共通なだけで、プラント発電用・家庭用・モバイル用なんかの用途によって、燃料の種類や作動の仕組み(主に、原燃料から水素を取り出す改質器の仕組み)が違うんですな。それでいろんな型に分類される、と。で、やっぱし一番注目しちゃうのは自動車用ね。これの動向はどうなっておるのか。
何種類かの型が検討されてるそうだけど、一番有力なのは「固体高分子型」だそうで。でも、本を読む限りじゃ実用化まで問題山積み。この本が出てから今までの間にも状況の改善が相当あったろうけど、いまだに燃料電池車って一般向けに市販されてないよね。燃料インフラが未整備なのとコスト。これに尽きると思うが、おいら的には、「思ったほど効率がよくない」という点が不満だったりする。
いや、だって発電効率がたった 35〜40% なんだもん。確かに普通のクルマのエネルギー利用効率は20%行くか行かないからしいから、それよりずっとましなんだけど、50% を超すと思わされてきただけに、これはちょっとショックだった。で、どうも 50% を超すってのは、据置型の燃料電池でコージェネレーション(熱電併給。電力と同時に給湯や暖房用として排熱を利用すること)をした場合のことだった。
この場合トータルで効率は 70〜80% にまでなるそうだけど、おいら、コージェネにはちょっと疑問を持ってるんだよね。そんなにうまくいくもんかい、と。だって電力の需要と熱の需要が常にぴったり一致するわけないじゃん。必ずどっちがか余るか足りないかして、ロスが発生するはず。そういうまやかし臭さを感じるわけですよ。実際、熱需要の方が大きい場合は、高価な燃料電池より、従来型の熱機関のコージェネレーションの方がバランスが取れるってことも考えられる。何がなんでも燃料電池がいいってわけでもなさそうなんだよね。やっぱ新聞記事だけが情報源じゃ見解が偏っちまうね。
話をクルマに戻すか。でね、コストの問題は弛まぬ技術革新でいずれ解決されるだろうと、研究開発者たちは信じて頑張ってるわけだけど、燃料供給インフラがちょっとまずい状況なのよね。ガソリンや軽油から水素を取り出せれば、当面は今までのインフラを使って、段々と燃料電池向けにもっと適した原燃料をガソリンスタンドに置いてもらうようにしていくって方向性でいいんだけど、クルマに搭載する条件の改質器じゃ、ガソリン・軽油ともに現状じゃかなり難しいらしい。で、本によると、どうせインフラ整備をしなきゃならないのなら、ということで、水素の直接供給と並んで、メタノール(メチルアルコール)が有力候補として挙げられてる。
メタノールを原燃料とした、固体高分子型燃料電池の改質器は、自動車用としてかなりいいものができあがってるらしい。あるいは、効率が少し落ちるけど、「ダイレクトメタノール式」っつう、改質器不要のシンプルな燃料電池も出来上がってきてる(もともとはモバイル用らしい)。
でもさ、やっぱし、ガソリンスタンドにメタノールを置こうって動きは、2007年現在で全くないわけよ。それよかバイオマス燃料のエタノール(エチルアルコール)の方が将来性があったりする。今、沖縄県のどこかの島で、バイオエタノール 3% 混合ガソリン(E3ガソリン)使用の実証試験が、その村を挙げて実際に行われてるそーだ。あるいはアメリカを走ってる、1999年以降に作られた自動車は全てE10(エタノール 10% 混合ガソリン)対応らしい。自動車用燃料の未来にはエタノールが選択されたわけですよ。メタノールじゃなく。で、将来的にはエタノール 100% 燃料がガソリンスタンドに用意されるようになりそげな気配。「燃料電池がわかる本」じゃエタノール燃料に関しては一切触れられてなかった。どーなるんだ一体。
なんかエタノールとメタノールって分子の組成が似てるから(エタノールの方が CH2 基が1つ多い)、改質器内でエタノールからメタノールを作って、それから水素を取り出せば良いんじゃないかとも思ったけど、ググったら、エタノール→メタノールの変換はそうそう生易しいもんじゃないらしい。やっぱしエタノールから直接水素を取り出すしかない。果たしてできるのか。そんでさらにググったら、できるらしいことが判明した。おお、すごいじゃないか。記事の日付は2004年2月13日。これじゃあ2001年発行の本に書かれてないわけだわ。おっと調べたら、同日付の朝日新聞にも記事が載ってた。全文転載。
燃料電池用水素
エタノールで効率的に生産
米大グループ開発
無害、環境へ影響少天然ガスやメタノールから製造されている水素を、ほとんど害のないエタノールで効率的に生産する方法が開発された。米ミネソタ大グループが13日付の米科学誌サイエンスで発表する。バイオマス(生物資源)によって生産されるエタノールから燃料電池用の水素を作ることが可能になれば、環境への悪影響をもっと抑えることができそうだ。
同グループは、エタノールと水の混合物を高温の気体にし、新触媒を働かせて100分の1秒で水素を取り出すことに成功した。反応効率はほぼ100%。この方法を使った装置はかさ張らず、車に搭載する燃料電池にも応用可能という。
エタノールは、米国ではトウモロコシなどの植物から年間約100億リットル生産され、ガソリン燃料に混ぜて使われている。同グループは「燃やして使うより、燃料電池用の水素に使った方が経済性が高い」とみている。
水素の製造や貯蔵に詳しい北海道大学触媒化学研究センターの市川勝教授は「エタノールはメタノールに比べて人体影響が小さく、腐食性も低いことから扱いやすい。水素製造の一つの選択肢になるかもしれない」と話す。
てなわけで、エタノール原燃料から改質器で水素を作って燃料電池でクルマを走らせる、という筋道が見えてきた。他にも、燃料電池にこだわらなくても、エタノールをエンジンで直接燃やしたりとか、エタノールから取り出した水素でエンジンを回したり、という手も考えられますわな。それなら、真打ちの燃料電池車が普及するまでの間、エタノールとガソリンの混合燃料でしばらく行けるんじゃないかとか、未来の展望が開けてきますなぁ。
けど、その方向性で頑張ってるのが海外で、日本が完全に後手に回ってるって現状はちょっと面白くない。そのことでまぁちょっと小耳に挟んだんだけど、どうも日本の石油元売各社が、エタノール混合ガソリンを拒んでるらしいんですよ。そんなことをされるとガソリンの売り上げが落ちてしまうからって。なんだかなぁ。
「だったら積極的にバイオエタノールの生産・輸入・流通市場に進出すればいいじゃないか、かつて自分達が石油市場に進出したときみたいに。それどころか、これからは資源枯渇と地球温暖化で先細りするのが目に見えてる石油業界は、バイオエタノールへの転身の準備を今からやっておかないと先がないのは目に見えてるだろ」と、常識で考えてそう思うんだが。なんか既得権にあぐらをかいて、今日明日の自分の利益だけを必死に守ろうとしてる浅ましい姿が見えてしまいますなあ(2007.4.27 補足:石油業界には石油業界のちゃんとした言い分があった)。
あと、ここまで日本が遅れてるってのは、役所が本腰を入れてないからってのもあると思う。甘ったれた石油元売業界の保護の面もあるかもしんないけど、おいらが「これが図星じゃないのか」と踏んでるのが、国税庁の難色(←憶測です)。エタノール 100% の燃料って、ガソリン程度に安くなきゃ商業的にやっていけないと思うわけでして、ていうか、アルコール燃料ってのはガソリンより発熱量が少ない→リッターあたりの燃費が悪いってことで、実際はガソリンより安くなきゃいかんと思うのよ。
一方、100% エタノールってのはつまりは酒なんですな。水やお湯で割ったりサイダーやトマトジュースで割ったりして、おいしくいただけちゃうんですよ。日本には酒税法ってのがある。この法律を根拠に支払われる酒税ってのは、国税の 3% ほどを支える、無視できない大事な税収源なわけです。国民が酒屋さんやスーパー・コンビニから酒としてエタノールを買ってくれないと、国税庁は酒税を取れない。ガソリンスタンドで買ったものはあくまでも燃料であって酒じゃない。
でも純度 100% なら実質は酒と同じ。リッター百何十円のガソリンより安いってんだから、必ず飲用に流用する輩が出てくる。そのぶん酒税の税収が減る。国税庁は役所の中でもかなりの権限を持ってる。ということで、この方面からバイオエタノール燃料普及の妨害がかかってるんじゃないかと勘ぐってみたり。国税庁の思惑としては、クルマの燃料には毒物のメタノールをむしろ普及させたいんじゃないかなとか。いやほんとただの憶測なんだけど、けっこう説得力あるような気が、自分ではしてるよ。
参考資料:これによると、「純粋なエタノールを燃料として利用する場合には、飲料への転用を防ぐため、メタノールなどを添加した変性アルコールの形で利用されることが一般的である」だそうで。ちゃんと対策してあるんだなぁ。ということで、国税庁の陰謀説はナシってことでひとつ。
映画『ジョジョの奇妙な冒険 ファントム・ブラッド』のサイト、おもしれー! ウィンドウ上でマウスをサッと動かすと、擬音の書き文字が出てくるぞ。しかもマウスの動線に沿って。しかも揺れてる。「メメタァ」が出るとなんか得した気分(笑) JavaScript だと思うけど、かなり高度な技を駆使しとりますなぁ。てか、サイトにここまで凝るくらいなら映画本編にもっと凝(略)
今日も午前中は焚火。午後はドカチンメットかぶって軍手はめて、ちょいと大掛かりな作業の監視役。そこでひとつ発見したものがあったよ。2007.3.22 の大型車への逆位相4WS(四輪操舵)、もう一部で実用化されてるんだね。それはクレーン車。↓こんなやつ。

でも実際の目的としては、構造上、ホイールハウスが充分に取れないから前輪の舵角を大きく取れなくて、それで仕方なく後輪も操舵してるって感じらしい。特段に、内輪差を少なくして小回りをきかせて、狭いところに積極的に入り込むためってなわけじゃないらしい。
ついでに今日は、間近で20トントラックも拝見できたんだけど、あれを4輪操舵するとなるとなかなか大仕事のような気がする。普通の状態で操舵する前輪は2輪なのに対して、後輪はダブルタイヤ2軸がけで合計8本ものタイヤを操舵しなきゃならないことになる。仕組みがかなり複雑になるうえに、パワステに食われる動力も半端じゃないような気がする。
単純化で言えば、日産の HICAS みたいにリアアクスル全体を回転させて操舵するって方法が考えられるな。つまり大型トラックで言えば、電車の台車みたいにリアアクスル全体が1本の縦軸で胴体から吊り下げられてるみたいな形にするわけだ。で、油圧で操舵する、と。通常走行時はリアアクスルの縦軸回転を固定すれば、直進安定性を保てる。つか、小回りが必要なときだけスイッチで 4WS 化するって方針でどうでしょ。
ああやっぱそれだめだわ。ハンドルのスエギリできないわ。狭い道に入るときはやり直すことも多いんで、スエギリができなきゃ意味ないわ。ということで、リアアクスルの2軸にもきちんとしたステアリングシステムを搭載しなきゃいかんことになりますな。これはめんどい。そう考えると、今までそれを思いついた人も多かったろうに、みんな結局この結論に達して、計画を断念せざるを得なかったんじゃないかな。でも、試作くらいは作ってもいいと思うが。
今日の作業でも、大型トラックは限られたスペースでの転回に苦労してた。逆位相 4WS があればもっと簡単に作業が進むだろうに、と。それと、道が狭いところでカーブを曲がりきれないんで、かなり迂回して現場に到着したんだそうで、やっぱしそういうときのために 4WS 技術は活用されるべきなんじゃないかと、本気で思ったよ。
ふーいようやく 八戸フォーラムかわら版 のレビュー原稿を上げたよ。『蟲師』に続いて今回も300字。題材は『ゲゲゲの鬼太郎』。ウエンツ瑛士主演のやつ。ウエンツ中心に書いたけど、監督の本木克英も注目だね。かわら版96号に載る予定だよ。
『蟲師』のときは大友克洋が脚本・監督だってのが不安だったけど、そこらへん自分を騙してかなりヨイショな記事を書いたらその内心の不安が見事的中して、2003.3.31 みたいな事態になっちまった。今回は監督さんに期待してますですよ。なんたって『釣りバカ日誌イレブン』の監督さんなんだもん。あの『イレブン』には感銘を受けたね(続けて12, 13も監督したそうだけど未見)。ハマちゃん気持ちいいくらいブッチギレまくってたもんなぁ。
てなわけで、今回は素直な期待感を背景に、気持ちよく原稿を書けましたです。あとさ、原稿に書くにはスペースの余裕がなかったんだけど、猫娘が田中麗奈ちゃんなんだよね。『暗いところで待ち合わせ』(2006)ですっかりレナラーになっちまったおいらとしては、これでもうダメ押し。「観ない理由なんてないね」って感じ。
「お子ちゃま向け映画なんてよく観に行けるよな」と自分でも思うけど、だからって面白いかもしれないものをムゲに見逃すって手もないでしょう。おいらの守備範囲である娯楽映画だし。実際、おととし観た『妖怪大戦争』も去年の『花田少年史 幽霊と秘密のトンネル』もすげぇ面白かったし。
最近はなんだか、変に大人ぶったハリウッドものの娯楽映画より、「楽しけりゃいーじゃん」的な日本の娯楽映画の方が肌に合ってる感じ。実際ツボを押さえまくってて楽しいし。ハリウッドの子供向けは「大人も楽しめる」のがコンセプトだけどやっぱ軸足は子供に置いてて、観ててちょっと物足りなかったりするんだよね。大人向け娯楽は先に書いたよーに、変に大人ぶってるというか気取ってるというかで、これまたおいらと合わないし。
そんなわけで、ウエンツ×本木の『ゲゲゲの鬼太郎』、おもっきし期待してますです。
人体の不思議。
みんなはどうか知らないけど、おいら、くしゃみで目が覚めたってことがない。例えばおいらは花粉症なんでこの時期はきついものがあるんだけど、寝てる最中にくしゃみで起こされたなんてことはない。朝起きた直後からくしゃみ鼻水攻撃が始まるわけだ。そういう点、花粉症も厄介者ながら、寝てる最中を襲わないとはなかなか紳士的ではあるな。
そういえば風邪を引いててくしゃみが止まらないときも、布団に入ると、気がつけば止まってたりする。ていうかそのまま眠れるんで、くしゃみが邪魔していないことに今さらながら気づいたぐらいにして。「くしゃみのせいで寝つけない」ってこと今までなかったもんなぁ。
つうことはあれかい、風邪や花粉症のくしゃみってのは基本的に、体を横にすると出なくなるもんなんかい。なんでまたそうなるのか。いや、便利で助かるんだけど、ちょっと謎に思ったもんだから。
今年初ジョギングしてきた〜。ついこの前まで寒かったもんだから、今年はかなり遅く始めることになったよ。とりあえず6kmね。去年の6月以来走ってなかったから、体が重い重い。ジョギングすると、走ってるうちに気持ち良くなってくるもんなんだけど、今日は別にそうはなんなかった。まぁまた体が走り慣れてくれば、自然に気持ち良くなるでしょう、と。
それにしても、今年は走ろうかどうか考えてたのよね。なんかもうめんどくて。なんぼ走っても全然やせないし。そんなわけで去年も、6月に色彩検定試験があるからってんで試験勉強を理由に走らなくなって、それっきり冬を迎えてしまった。
そんなテンション低い状況をブチ破ってくれたのが、今日観た映画『リトル・ミス・サンシャイン』。これ観たとたん何かしなきゃいけない気分になって、とりあえず走り初めしてみました〜。
家族かぁ。いいもんだなぁ。おいらんちはここんとこ長らく母親との単調な2人暮らしが続いちゃって、映画に出てくるフーヴァー一家が羨ましくなっちゃったよ。とはいえ主人公のオリーヴちゃん以外みんな問題を抱えてるから、「端から見ての羨ましさ」なんだけどさ。
おいらは似てるところがあるかも。この映画の登場人物、悩み迷えるドウェイン君と。彼は、空軍のテストパイロット(最新鋭の試作機を操縦して、どこに潜んでいるか分からない不具合を見つけ出す、命がけの職業。おいらも昔ちょっと夢見たことがある)になるという夢を叶えるため、憧れのニーチェの真似をして「沈黙の誓い」を立てて何も喋らないんだけど、それは周りに対する言い訳でしかないのは明らか。
テストパイロットの夢は本物だけど、喋らないのは自分の人生や境遇に対する不満や諦めの表明。だから何をしても何も楽しくない。ただテストパイロットになる夢だけが、彼を支えてる。と同時に、その夢にあまりにも固執・依存してるために、誰も(家族でさえ)受け付けない性格になってしまった。
ドウェイン君の夢があっけなく破れてしまったとき、彼を慰めることができたのは純粋無垢なオリーヴちゃんだけだった。まぁいたいけな子供に当たったってしょうがないしな。それにこの子はこれから自分の夢を叶えようとしてるんだから、仕方なく付いてきた旅の中で、初めて彼女を応援してあげたくなったのかもしんないな。そこらへん、「それぞれが問題を抱えている家族」とは言え、いい育ち方してるよ。芯のところじゃまともな大人になるべく成長してるってば。ドウェイン君と同じ歳(15歳)のおいらだったら「お前の夢だって叶うもんか! 叶うわけがねぇ! ケッ!」とか暴言吐いてそう orz
実際、自分が一心に追い続けてきた夢がいきなり絶たれたら、そうそう落ち着いてもいられないと思うんだけど、そこは映画。映画の流れのままに受け入れましょう。その時点で既にこの映画にハマッてしまってたのが今さらになって分かった。で、『リトル・ミス・サンシャイン』コンテスト会場でオリーヴちゃんの両親が右へ左へと大忙しの間、ドウェイン君と、彼の叔父のフランクさん(自殺未遂の直後にこの旅に出る羽目になった)が海辺で語り合う場面が印象的だったな。その前におじいちゃんが旅の始めに車の中で、「経験者の言うことを聞け」なんて押し付けがましくドウェイン君にいい加減な演説をふっかけた時とは違って、今度はドウェイン君は素直。フランクさんは自分が研究の専門としてるプルーストからの引用で、こんな風なことを言ってた。
「十代のハイスクールでの最悪な気分や生活は全て、その後の人生の重要な糧となる。幸福な生活にはそのような糧など何もない」
おいら的には極論っぽく感じるけど(特に最後のところ)、夢破れて憑き物が落ちたようなドウェイン君はそれを受け入れる。なんかこう、彼の人生がこれから大きく開けた瞬間に思えたよ。もしトントン拍子でテストパイロットになったら決して味わえない、もっと大きくて価値のあるものを、きっと彼はその後の人生で手に入れることだろうなぁ。ラストで一瞬見せる、車の中での彼の笑顔がそれを保証してるみたいで、スカッと楽しめた映画だったよ。
翻っておいらの場合はどうか。十代のみならず二十代以降も思うがままにならぬ、我ながら情けない負け犬人生を歩んで、いまだに悪戦苦闘中で出口が全く見えない状態なんですが。ドウェイン君は夢を失った後すぐに立ち直れたけど、やっぱそこは映画だよね。現実はそんなに甘いもんじゃない。けどそれはもしかしたら、人生の大きな果実がもうとっくに目の前にぶら下がってるのに、いつまでも過去に捕われてるおいらの意固地な心が、それに気づかせてないだけのような気がしてきて。こう、この映画を観終わったあたりからフツフツとそういう気がしてきて。
で、今おいらが何をなすべきなのかさっぱり分からん状態だったけど、何かしたくてしょうがなくなっちゃったんで、今年はやるかやらないか先月あたりから迷ってたことをしてみたってわけ。「とりあえず走るぞ〜ッ!」。
しかしさ〜、以前、ジョンベネちゃん殺害事件の容疑者が捕まったことをネタに、アメリカの美幼女コンテストに対して違和感を表明したわけだが(2006.8.23)、やっぱあの習慣はいただけないと思うぞ。そのコンテストの様子が映画で出てきたんだが、思った通りというか、おいらの目からするとあのギンギラギンに着飾った幼女たちがステージに並んでる様子は、マジで異様な光景だったぞ。アメリカは性犯罪に対する処罰が厳しいらしいけど、この風習が異常性犯罪の温床になってる気がする。なんだかそれっぽい観客も映画に出てたし。
「第27回」とか何とか言ってたから、こういうのはそれなりに伝統があるんだろうけど(アメリカは国の歴史が短いから、何でもかんでも「伝統」にしたがるよね)、親バカもけっこうなことなんだけど、始めはきっと牧歌的なもので、子供の素の可愛らしさを競うものだったんだと思う。それが髪も服もメイクもあんなゴテゴテに飾り付けて無理矢理セクシーさを強調させて(水着審査もある)、当初の趣旨から相当エスカレートしてしまってるんじゃないかと思うわけ。伝統だろうが何だろうが、この現状と今の世相を鑑みて、子供の安全と健康な成長のために、こういう大会を一切やめちゃうというのも、ひとつの勇気ある社会的決断だと思うが。
寝てるときはくしゃみしないっての、他の人にも当てはまるらしい。ここの Res にそれっぽい話題が出てる。ふむふむ、シャックリも寝るときは止まるもんなのか。
NHK の統一地方選の選挙速報を見てたら夜中過ぎてやんの。だってさー、青森県議員選、八戸市地区の最後の議席がなかなか決まんないんだもん。何をもたもた開票やってんだか。確定するのが遅かったのは他に、むつ市地区ね。
まぁおいらは特に支持政党とか支持者を持ってないんだけど、親戚から「どうしてもこの人に入れてくれ。いつもギリギリなんだ」と頼み込まれたんで、その人に一票入れてやったんだわお情けで。そしたらほんとに最後の議席を争って大接戦を展開しちゃってさ。
でも速報を見ると、未定組の中で一番の得票なわけよ僅差だけど。で、こりゃあ通ったな、と安心してたらさ、「むつ市地区の最後の議席に当確が出ました」って、こっちも接戦だったんだけど、テレビに出てる得票数じゃ下に位置してる人の方に当確が出ちゃってこれが。
お、おい、こりゃ八戸も分からんぞってな雲行きになってしまって。で、がんばって 24:30 あたりまでテレビを見てたんだけど八戸の最後の議席が一向に埋まらないんで、明日仕事があるし義理で投票しただけだからもうどうでもいいや、てなことで、今これ書いてアップしたらソッコー寝るです。昨日の日記がんばりすぎて、今日はあんまし書く気が起きないし。
そんではおやすみなさいませ〜。とりあえず結果は明日の新聞で確認するべ。
都知事選は石原君の圧勝だったね。しかし都知事選の前哨戦の過熱報道、どうにかならんかったんかねぇ。全国版のニュースでガンガン取り上げてたんだけどさ、おいら都民じゃないから全く関係ないわけですよ。うちの町にオリンピックが来るわけじゃなし。日本の大部分の人(都民以外の人)には関係ない話題なわけですよ。だって都知事選の選挙権は都民にしか与えられないし。それを、東京だからってだけで全国版でニュース垂れ流すマスコミの姿勢に疑問を感じたなぁ。確かに東京は特別な地域だけど、知事選に関しては、東京だって単なるひとつの地方でしかないじゃん。
そこらへん、マスコミの本局も東京に集中してるもんだから、「東京の話題=日本全国の話題」っつう勘違いが横行してたってことですな。みんな東京に引きこもって同じ勘違いしてりゃ、誰も気付かないってことで。
今回の都知事選じゃ、全国系マスコミのそんなマヌケっぷりがよく拝めました、と。全国系マスコミで、東京から出て行って、東京を客観的に報道しようって骨のあるやつはおらんのかね。ちなみに、「東京は大震災がいつ起きるか分からないから」と本社機能を我が青森県八戸市に移転した、骨のある全国系企業ならあるらしいぞ。
ついでに言うと、海外マスコミの日本支局も東京に集中してるから、「東京発の情報=日本全国を代表する情報」だと思われてるんじゃないのかねぇ。東京ってのは日本の中でもかなり特異な地域なんだから、それを日本の標準的状況の全てだと思われるのは、日本人として大変に心外なんですが。欧米系マスコミは日本のマスコミより質が高いと思われてるけど、結局日本のマスコミと同じ罠にハマッてますですな。欧米人も案外と頭悪いですな。
おとといに続いて今日の夜も走ってきたわよ〜。昨日買ったばっかりの真新しいシューズで。昨日は、右の足の裏が痛くなっちまって休んだんだわ。おとといかなり久しぶりに走った&シューズが古くなって、衝撃吸収力が落ちてたってのが原因かと。
んで、今日の夜になったら痛みが引いたんで8km走ってきた。おいらの場合、やっぱ6kmだな、あのバルブが開くポイントは。何のバルブかって、脳内麻薬の(笑)。いやほんと絶対脳内麻薬が出てるってばw
ジョギングの気持ち良さは、実際やってみてどんなもんか初めて分かったよ。その前から「ジョギングは気持ちいい」とは聞いてたけど、それは普通のスポーツと同じく「汗をかく or 体を動かす爽快感」だと思ってたのよ。でも違ってた。気持ち良さの質が明らかに違う。こりゃもう爽快感なんてもんじゃなく、快楽そのもの。あまりの快感に、終盤はヘラヘラ笑いながら走ってるもん。なんかもうスポルツメンシップから外れた邪道なニオイさえするような……。
普通、単純作業を何十分も続けても気持ち良くなったりなんかしないもんだけど、「自分に合ったちょうどいいペースで走る」っつう単純作業の場合だけは状況が違ってきちゃうんですな。ホント何なんだろ、ちょっとヤバめなあの快楽は。苦しさを紛らわせるために脳内麻薬が出てると解釈しても、いささか奮発し過ぎじゃないのか? 苦しさを紛らわすなんて程度を軽く超えて、全然苦しくも何ともない。それどころか、ただ、ただただキモチE〜。で、いつまでも走っていたくなっちゃう。でもあんまし走りすぎるとマジで体が持たないんで(走り終わって初めてダメージに気づくのだ)、泣く泣く無理しない程度のところで切り上げちゃうわけです。
ちゅうか、それでもやっぱり無理があったみたいで、今日の午前中まで痛かった右足の裏が、夜走ったらまた痛くなっちった。こりゃあ骨だなキてるのは。誘惑に負けて毎晩走り続けると、手が付けられなくなるくらいまで痛くなるってパターンだな(3年前に膝で経験済み)。
これがまた不思議なことに、普段の生活をしてる間は痛くて歩くのも億劫になるほどなのに、ジョギングし出すと途端にその痛みが消えちゃって、それで患部にますますダメージを与えちゃうのだ。脳内麻薬恐るべし。患部には走り始め直後から作用するらしい。残念だけど明日は養生のため走るの休みだな。患部に湿布でも貼っとこ。あさっては患部の回復の具合を見て、走るかどうか決めよっと。
つうことで、端から見ると「あんな単調な運動の何が面白いんだか」のジョギングには、「快楽に耽っていられる」というヒミツがあったことを、ここで一般公開しちゃうのだ。ニヤニヤしながら走ってるジョガーを見かけたら十中八九、脳内麻薬ジャンキー状態です。その時はどうか生温く見守ってやってください。
先月の話題だけど、"dwarf planet" の和訳は「準惑星」になったんだそうで。
去年、天文学の話題のくせに世界中で大騒ぎになった、冥王星の「惑星」からの降格。で、かの星は新たに定義された "dwarf planet" のひとつ、と分類され直したわけだ。ニュースになってた昨年当時、日本のマスコミはとりあえず仮の訳語を作って、それを報道した。「矮惑星」「矮小惑星」がそれ(「矮小惑星」は読売新聞でのみ確認。他においらが目にしたマスコミは皆「矮惑星」としてた)。そんで最近、その道の専門家が集まって相談して、「準惑星」という単語を作り出して、それを推奨することにしたんだそうだ(資料)。
3月中に読んだその話題の新聞記事によると、「矮」は否定的なニュアンスもあるからってんで、中立的な「準」が採用されたそうな。でもさでもさ、既に日本語化されてる天体の分類で、「白色矮星」、「褐色矮星」ってあるんだけど。どっちも原語で "dwarf" って単語が使われてるから、整合性を考えると「矮惑星」のままの方がよかったんじゃないかと思うんだが。たぶん仮訳段階でも、"dwarf" が付く天文用語で既に「矮星」という漢字が当てられてるのを参考にしたんだと思う。そんな状況で今さらながら「『矮』は否定的なニュアンスがあるからダメ」っての、なんかちょっとおかしいんじゃないの?
"Dwarf" =「準」となると、白色矮星、褐色矮星はそれぞれ「白色準星」「褐色準星」ってことになる。ところがどっこい「準星」って単語もまた既に "Quasar(クエーサー)" という天体の日本語訳として使われてたりして、なんかかなり混乱の様相を呈したりする。
素直に "dwarf planet" を「矮惑星」に決定してれば、こういうわけ分かんない事態も防げてすっきりしてたと思うんだが、誰に気を使って「矮惑星」が「準惑星」になっちまったんだろ。まさか冥王星降格でショックを受けたアメリカに気を使ってってわけじゃないと思うが(冥王星はアメリカ人が唯一発見した「惑星」ってことで、かの国では愛着が強かったらしい)。そもそも日本語だけの問題だし(同じ漢字圏の中国の判断が気になるけど)。
天文学会(天体物理学会)の標準語は英語だけど、まぁローカル言語が英語にきっちり即さなきゃいけないってわけでもないからね。日本じゃ一般に「星」= "star" と思われてるけど、ほんとは英語の "star" は「恒星」のことであって、同じく夜空を彩ってる「惑星(planet)」とは、英語圏だと天文学に別に興味のない人たちでもフツーに区別してるわけで。そこらへんの認識が英語と日本語で決定的に違ってるのにそのまんま通ってしまってる。だからもう「日本じゃ "dwarf planet" は『準惑星』と呼びましょう」と決まっちゃったら決まっちゃったで、それに慣れていくしかないんだけど、それでもどうにもしっくりこないなぁ。ホント誰に気遣った結果なんだ?
一連の流れからすると、英単語の "dwarf" には否定的なニュアンスはないっぽいな。『白雪姫と七人のこびと』の ♪ハイホー ハイホー の「こびと(小人)」も "dwarfs" だしな。って、確認のために研究社英和中辞典第6版を引いたら、
a (特に, 頭が大きく手足が短い)小びと.b (おとぎ話に出てくる)醜い[グロテスクな]小びと.
だそうで。ネガティブな意味もちゃんと入ってたのね。グロテスクと来ましたか。だったら日本語訳もそこまでの意を汲んで、堂々と「矮惑星」で決めても良かったはずなんだが。あと、
特別に小さい動[植]物, 矮性(わいせい)植物; 盆栽(ぼんさい).
ってのもあった。盆栽も dwarf なのか……。
走りてぇ〜。ジョギングしてぇ〜。脳内麻薬の快楽を味わいてぇ〜。でもだめ。今は養生中。まだ右足の裏とくるぶしあたりに違和感があるから、このまま走ったらまた痛くなっちまう。しかも2回目に走った後、いつまでも汗で濡れてたトレーナー着てたもんだから風邪引いちゃってヘクシッ! うい〜。こいつも治さにゃいかんな。
つうことで、走りに対する(いささかよこしまな)意気込みを、今日はこの日記で晴らしちゃおうって腹。長距離走の花形といえばマラソンですな。おいら程度のジョギングとは全く次元が違うんだけど、まぁ憧れちゃうわけです。おいらの場合、時速8km程度なんだけど、マラソンの選手ってのはその倍以上の時速20kmで、おいらの5倍の距離を一気に走り切っちまうんですな。いやほんと、こうして数字で比べると、フルマラソンがいかに苛酷なスポーツなのかよく分かるわ。
他に苛酷さを示してるのが、競技途中での給水。あの、テーブルに置かれたコップ入りの水。ところどころに用意されたこいつを走りながらひっ掴んで、飲んだり頭からぶっかけたりしながら彼らは競技を続けますな。で、オリンピック中継なんかでよく見るのが、水を取り損ねてしまう人たち。そのときの彼らの悔しそうな顔ったらない。あれをどうにかできないものか。
すぐに分かるのが、選手たちのスピードが速すぎるってこと。時速20kmつったら、普通の自転車の巡航速度だよ。あんなスピードで、止まってるものを手で掴むってのは至難の技だって。そりゃ失敗もするだろうに。
一番いいのは、水を積んだワゴン車で並走して、車から選手に水を手渡すってのだろうけど、全ての選手に行き渡らせるのが難しい気がする。やっぱし要所要所にテーブルを用意してコップ入りの水を出しといて、足りなくなりそうだったらその場でどんどん新しいコップに水をついでテーブルに並べるっつう、現行の形に落ち着きますな。ところがそれじゃ取り損ねが発生してしまう。そこでひとつ考えた。
回転寿司のベルトコンベアを使えないか。
それで速度差を相殺できないか。
水を準備するスタッフは、ベルコンの折り返し側でどんどん水入りコップを置けばいい。これは便利そう。でも真っ先に思いつくダメ出しが、「それじゃ遅すぎる」。
そうだよなぁ。最低でも時速10kmくらいは出てくれないと意味ないよな。で、マラソン専用の特別仕様だとして時速10kmでベルコンを回すとすると、今度はベルコンの折り返し地点で、遠心力でコップが倒れてしまう可能性も出てきますな。そしたらコーナーにはガードレールを付けて、なんとか倒れないようにすればよろしい。ガードレールとの摩擦抵抗で後ろ向きに倒れてしまうかもしれないんで、ガードレールの表面はピカピカに磨き上げにゃいかんな。あるいはローラーを立てたのが並んでるみたいなガードレールにしちゃうか。
これだと現行の方式に比べて装備が圧倒的に大がかりになってしまうけど、選手のことを考えるとそうしたほうがいいと思うが。幸いマラソンは人気競技なんで、国際大会クラスだったら、準備できないって程でもない気がする。日本陸連あたりがメーカーを通して製作・管理して、国内各地の大会に有料でリースするって形でどうでしょ。製作に当たっては、ランナーの意見を採り入れながら設計を詰めることになると思われ。その過程で特許も発生するだろう。そして、その便利さが認められれば、国外でもこの機械を導入せざるを得なくなる。日本から世界に輸出することになりますな。
いいことじゃありませんか。マラソンなんつう、オリンピックの花形競技に日本の技術が貢献できるチャンスですよこれは。
え? そこまでしたがる主催者がいるもんかって? いや〜いると思うよ。どこの主催者も、自分とこの競技で世界記録が出ることを望んでるはず。この機械は競技者の「水を取れなかったらどうしよう」という不安やストレスを減らす効果もあるから、そのぶんのびのびした気分で競技できる。それが記録に結び付くってことも充分考えられるって。
てことで、どっかの回転寿司ベルコンメーカーさん、日本陸連や、東京オリンピック開催を狙ってる都知事あたりに提案してみたらどうですかねこれ。
Wikipedia 内の、「未確認生物一覧」っつうページに行き当たった。いわゆる "UMA" ってやつね。これが面白くて。
水棲系が多いけど、やっぱスリリングなのは地上系だね。いや、だってそこらで出し抜けに出会ってしまうかもしんないじゃん。トカゲ男なんかにいきなり襲われたらどうするよ。かなり獰猛らしいぞ。もうパニックもいいとこだぞ。しかし米軍にケンカふっかけるなんて、よっぽど肝が据わった怪物ですなぁ。
モスマン (蛾男) もキョーレツだよなぁ。時速160kmで逃げるクルマを、同等のスピードで飛んで追っかけてきたってんだから恐え!! 状況を想像するだにマジ恐くなる。でもさ、お膝元のウエストヴァージニア州じゃかなりノリが軽いよね。ライダー怪人風の像なんか建てちゃって。目撃情報じゃ「手がない」って言ってんのに、怪しい人っぽい手つきの手がおもっきし付いてるあたりが笑える……。腹筋もしっかり6つに割れてるし。完全に観光資源扱いですな (^^;) かのジョン・デンヴァーが名作 "Take Me Home, Country Roads" で ♪Almost heaven 〜と歌った彼の故郷ウエストヴァージニア州、なかなかやります(笑)
んでさぁ、そんな地上系未確認生物の中でもとびきり衝撃的なやつ、そいつが エルダーモンスター(こいつもウエストヴァージニア出身なのかよ……)。何が衝撃的かって、目撃者の談話が。
目撃者さんには悪いけど、読んで笑ってしまった (^^;) で、目撃者は「重度の鬱状態に。半年後、行方をくらまし、現在も行方不明」だそうで。笑いごとじゃないですな。んでどんなたたずまいなんだよそのエルダーモンスターってのは。そして彼が描いた絵が載ってるページを発見。んー、確かにこんな奇っ怪なやつといきなり出くわしたら正気を保っちゃいられないと思うけど、普通「びっくり仰天して逃げる」だよなぁリアクションとしては。それが、見た瞬間から重度の鬱になるってのは何なんだ一体。人間の脳にそういう影響を与えるフェロモンでも分泌するのか? なんかほんと謎が謎を呼ぶよなぁ。実害がある例も珍しいけど、精神的な害を及ぼすってあたりが、他の UMA たちと決定的に違う恐さを醸し出してますなぁ。
上に挙げた3例はいずれもアメリカで目撃された(とされる)やつなんだけど、なんかもうやっぱ、日本のツチノコなんかよりいずれもスケールが違う。そんなところで「さすがアメリカ」なんて感心したぐらいにして。
いやーなんだか今日はこの「未確認生物一覧」で楽しまさせていただきました。
思い出した。このページにたどり着いたのは、一時期話題になった「スカイフィッシュ」のその後の顛末を知りたかったからなんだわ。なんか結局は「昆虫が飛ぶ残像がビデオの機構上それっぽく写っただけ」ってことで話が決着したと思ったんだけど、一応 Wikipedia に当たってみたら、それだけじゃ説明できない事例もあるんだそうで。
マンガ「ジョジョの奇妙な冒険 第六部 ストーンオーシャン」で、こいつを自在に操る敵が登場するんだけど、その後に「スカイフィッシュの正体はビデオのモーションブラーで決まり」って雰囲気になっちゃって、かなり作品が傷ついちゃったなぁと残念に思ってたんだわ。でも、まだ存在の望みは断たれてないことが分かって、ちょっと安心してみたりw
2013.8.3 追記: エルダーモンスターの正体、判明すますた。詳しくはコチラ。
職場にて、焚火して灰にしなきゃなんない木製品群を新たに発見。ってことで今日はその一部(結構な量だったけど)を燃やした。
人間、見たくないものはなかなか見えんもんですな。3月中に木樽や木箱を燃やしたときは、焼却炉を使えた。だからホイホイ実行できた。で、今日意を決して燃やしたものはなかなかの大物で、焼却炉に入り切らないものだった。てなわけで職場の敷地内の空いてるところで燃やさなきゃならなくて、点火に手間がかかるんじゃないかとか火の粉がやたら飛んで手に負えなくなるんじゃないかとかいろいろ考えてしまって、どうもあんましそのことを考えないように考えないように、と自分を持っていってしまってたらしい。そいつの存在は分かってたんだけど、いずれ焼却しなきゃいけないもんだと分かってたんだけど、目に入らないようにしてたというか考えないようにしてたというか。それで意を決するのに今までかかってしまった。
で、その作業をすべく、木樽や木箱があったのと同じ高所に登るまで戸惑うこと5分。現物(ふすまの枠をゴツくしたみたいなもので、紙じゃなく金網が打ち付けてある)の大群と向き合って「本当にこれでいいのか?」と悩むこと5分。全部下に投げ落としたブツを見つめながら「なんかとんでもなく馬鹿なことしようとしてるんじゃないか?」と考え込むこと10分。でもここまでやっちゃったんだから、うまくいくことを祈って最後までやっちまおう。
いざ燃やしてみたらあっけなかったというか。案ずるより生むがナントカ。風が弱かったんで、段ボールを焚き付けにしての点火は今日も成功。燃える先から台車でブツを運び出しては火にくべまくる。周りの枯れ葉に延焼し始めたんで、そういう燃えそうなやつは集めて火にくべて延焼を止めた。最後のあたりで雨がポチポチ降り出してきたんで急ピッチで作業を進めて、ちょうど全部燃やし切ったあたりで本降り。消火作業の手間が省けたよ。
んで、これで焼くもん全部焼いた〜っとせいせいしてたら、他に焼かにゃならん大物(でっかい樽とか木製パレットとか)がまだまだあったことをそのとき思い出したぐらいにして。これまた見ないようにしてたやつらね。焚火場所の確保のためには、今日の燃え残りである金網をどっかに持ってかないといかん。また段取りを考えんとなぁ。ああめんど。
要は、やったことないことを想像で段取るのがめんどくて、それが嫌だっつうそんだけのことか。「積極的な性格」。「大胆な行動力」。こういうの、どーすりゃ獲得できるんすかねぇ。
今年夏に打ち上げられる日本の月探査機 SELENE(セレーネ)、署名とメッセージ募集に続いて、愛称を募集中だよ。応募はこちら。
しかし、"SELENE" っててっきりそれが愛称なんだとばっかし思ってたんだけど、実は "SELenological and ENgineering Explorer" の略なんだそうで。ここで単語 "Selene" を辞書で引いてみると、
【ギ神話】 セレネ (月の女神で Hyperion の子; ローマ神話の Luna に当たる).
だそうで。どう考えてもこじつけっぽいんですけど (^^;)。でもそれが計画名ってことで、愛称はいつものように、ひらがなで(つまり和名で)行こうってことらしい。てことは今回も、打ち上げが成功して軌道に乗った時点で発表されるのかな。ああでも同じく愛称を公募した陸域観測技術衛星 だいち(計画名 "ALOS")は、打ち上げ前に愛称の公表があった気がしたなぁ。どれどれ、JAXA メールマガジンを検索してみるか。
送信日時:06.1.11 3:03 PM
陸域観測技術衛星(ALOS)の愛称について
平成18年1月19日(木)に、種子島宇宙センターからH-IIAロケット8号機で 打上げ予定の陸域観測技術衛星(ALOS)の愛称は、厳正な審査の結果、下記の とおり決定しました。多くの方々からのご応募、ご声援をいただきありがとう ございました。
記
1.決定愛称名 「だいち」(英語表記:DAICHI)(以下略)
おお、やっぱし。それじゃあ今回の SELENE も愛称の事前公表の可能性ありってことですな。それにしても SELENE 計画、遅れに遅れたけどとうとうここまで来たか(万感)。90年代から計画が進められてて、はじめは着陸実験機もセットで開発されてたのが、H-II ロケットの打ち上げ失敗を受けて、リスク分散のため軌道周回機と着陸機が別々に打ち上げられることになったのがケチの付き始め。その後、不況による予算削減のあおりで着陸機がお流れになって、軌道周回機のみになってしまった。
それと、これとは別に計画名 LUNAR-A っつう月探査機の計画もあったんだけど、そっちは技術的な問題から延期に次ぐ延期で、とうとう最近、計画中止決定の憂き目に遭ってしまった。そんな逆境の中を SELENE 計画は生き残ってきた。しかも H-IIA ロケットまで打ち上げ失敗して、原因究明と対策に時間を取られたってことで、H-IIA で打ち上げられることが決まってた SELENE は、ただひたすらその出番を待たされてきた。
そんな難産だった計画なだけに、是非とも今回はノートラブルでの運用をお祈り申し上げます。日本の宇宙探査は、太陽系内の直接探査に限るとけっこう傷だらけの人生を歩んできてる。80年代のハレー彗星探査機2機は成功を収めたけど、機体が大型化してからの、火星探査機 のぞみ(致命的トラブル発生で火星周回軌道に到達できず)にしても、現在運用中の小惑星探査機 はやぶさ(小惑星の試料を持って今年の6月に帰ってくる予定が、トラブル発生で2010年帰還予定になってしまった。しかもいつまた壊れるか分からないので予断が許されない状況)にしても、どうもトントン拍子には行ってない状態。
そこへ来て日本の科学探査機としては過去最大の今回の SELENE。別天体の直接探査とはいえ、月というまあまあ近いところが目標だし(それでも H-IIA ロケットにしてみれば今までで一番の遠出)、初めて行くところじゃないんで(天体の引力を利用した、スイングバイという技術の獲得のための衛星 ひてん が月に訪れてる。道中、はごろも という小さな衛星を月の周回軌道に投入した。NASA と共同の "GEOTAIL" っつう衛星も、月スイングバイを何十回も繰り返した実績がある。さらに火星探査機 のぞみ も月に接近してスイングバイを2回行った)その点じゃ比較的ラクなミッションかと思われ。でも大きいっつうことは仕組みも複雑っつうことで、今までの実績から考えても、トラブルが心配になってこようってもんです。どうか何事も無事でありますよーに (-人-) なむなむ
小惑星探査機 はやぶさ がそろそろ、「地球へ向け、発進!」の運びらしい。2005年12月の通信途絶と2006年1月の通信復活以来、何もせずにただ地球帰還のタイミングを待ってたわけじゃなく、探査機の内部状況の把握、大気圏再突入カプセルのフタ閉め(復活後、これが技術的に一番スリリングだった)、地球に向けての新たな航行プログラムの作成と書き換え、イオンエンジン(宇宙航行用にはやぶさに残された唯一の手段)の試運転その他、山積みのやらなきゃならないことをようやく全部クリアしての、万全の態勢での復路再出発ってことらしい。
2005年7月の到着以来、長いことお世話になった小惑星イトカワに別れを告げる頃合いになりましたなぁ。プロジェクトマネージャーの川口淳一郎教授はそれでも、「運用は厳しい」とまったく気を緩めてないらしい。2010年に地球帰還予定っつうから、これから3年の長い道中、何も変なことが起きませんよーに (-人-) なむなむ
そうそう、はやぶさの本体が、地球帰還時に大気圏に突入することがほぼ決まってしまったらしい。本来はイトカワの試料が入ってる(と思われる)カプセルだけが地球に帰ってきて、はやぶさの本体はそのまま人工惑星になる予定だった(「今となっては」だけど、はやぶさの状態が良ければ、カプセルを地球に届けた後、別の小惑星の探査に向かうことも考えられてたそうで)。けど、姿勢制御系統がほぼ死んでしまった現状だと、予定してた距離からのカプセル投下を行うと誤差が大きくなってしまう。カプセルはオーストラリアのウーメラ砂漠に落とす予定だけど、街に落ちてしまう可能性が出てきた。
ということで、地球にぎりぎりまで近づいて、命中精度を上げてからカプセルを投下する必要が出てきた。で、その線で計算すると、はやぶさの本体も大気圏に突っ込んで消滅しまうことが確実になってしまった、と。はやぶさのその波乱に満ちた運用を思うと、かえってこの壮絶な最期がふさわしく思えてしまうなぁ。
そーいえばなんか1年くらい前から、うちの COMPAQ 333MHz に Linux 入れてるんだよね。で、結局 SETI@home 専用機にしてしまって、全く手ぇつけてないわ。現状から見た将来性を考えると、FreeBSD より Linux の方が実用的なのは分かってるんだけどさ。
いや、Linux を学ぼうって気がないわけじゃないんだけど、FreeBSD の方にようやく慣れてきたあたりでさ。で、こういう自分にとって新しい OS に挑戦する場合、一番問題になるのがアプリのインストール方法だってことが分かった。FreeBSD も Linux も PC UNIX なんで基本的なコマンドは同じでいいんだけど、アプリのインストール方法が全く違ってて、それで二の足を踏んでるとこ。
やっぱフリーソフトは常に最新版を使いたいじゃないの。で、PC いじるならまずウェブブラウザじゃないの。…… Linux での Firefox 2.0 へのアップグレード方法がいまだに分からん (T_T) Linux(Fedora Core 4)のインストールソフトに付いてきた Firefox 1.0.x なんてもう嫌だ。ていうかはじめから嫌だった。1.x → 2.x は単純なアップグレードじゃなくてインストールし直しが必要なんだけど、やり方が分からん(単純なアップデートはインストール CD とセットの教科書にやり方が載ってたけど、1.0.x 内のアップデートしかしてくんなかった)。
FreeBSD だと ports 関連の装備で全部そこらへんをやってくれるんだけど、そいつは FreeBSD のみの機能。Linux だとなんだか何種類かインストール方法があるらくして、どうも覚えるのがめんどい。基本的にソースコードをコンパイルする ports と違って、Linux の rpm なんかだとコンパイル済みバイナリを扱うのが普通らしいから、時間がかからなそうで便利そうではあるんだけど。でもなんかこう、目の前に引かれた一線を踏み越えられないっつうか。
はーでも、世の中で稼いでいくためには PC を扱えなきゃいかんわけで、おいらは Windows の扱いが全くできないわけで(無料 OS に慣れっこになってしまって、今さら Windows やら専用アンチウイルスソフトやらに自分からカネ払う気がしない)、Mac なら多少いじれますったって使える現場は限られてるわけで、そうなると、理屈で考えると Linux 習得が最善ってのは目に見えてるのになぁ。今ハマッてる FreeBSD は、仕事の道具として使うにはまだまだ洗練されるのを待つ必要があるしなぁ(←主観で言ってますよ)。
それに、PC ってやつを Mac で学んできたせいか、基本的に教科書を読みたくない人に育ってしまったし。甘ちゃんもいいとこですな。つうことで、これからは Linux 学習に全力を挙げるのだ。サーバは無理としても、Linux をクライアント機として使いこなせるようになるのだ。
と目標を掲げてはや1年(以上)。いつになったら到達できることやら。そうこうしてるうちに Linux の方も、Fedora Core 5 がとっくに出てるし。なんもせんうちに時代に取り残されていくぅ〜。
でも勉強めんどくさ。
そそ、この さんでー立体写真館ってサイトはさ、歴史はけっこう長いけど(1999年からやってます)なんかこう、個人サイトとして決定的な何かが足りないよーな気がしてたんだわ前から。それは、
かなり今さら気づいてしまった (^^; そうゆーのがないんだよね現状じゃ。読む側からすれば、特に初めていらした方からすれば、どんなやつがこのサイトをやってるのかが幾分でも分かった方が親しみが持てるし、たまたまたどり着いたこのサイトでどういうことをやってるのかが明記されてた方が、分かりやすくていいに決まってる。こっちの都合で言えば、リピート率が上がるってこと。
でも自己紹介とかそうゆーの苦手でなぁ。他の個人系サイトさんって、そのあたりが充実しててしかも面白いんですわ。んで、そこらへんのそうそうたるサイト樣方に匹敵する自己紹介やサイトの方針表明を作る自信がなくてですね、せっかくその必要性に気付いたのに、あんまし乗り気じゃなかったりする。ほんとは別に匹敵してなくても全然構わないんだよね。いつだって書き換えられるんだから、いったんテキトーなの作っといて、後でどうにでも作り直せばよろしい。
と分かってるのに、やっぱし作る気が起きない。なんつーかもう、この日記がつまりこのサイトの方針表明であり運営者の自己紹介であるって感じで勘弁していただけないかなとか。いやそれだと無駄に膨大だろ (-▽-;) つうかもう最近、日々の日記を書くだけでヘロヘロの状態でさ、他に手を回す心理的余裕がないっつーか。そのうえあんまし面白いネタ書けてないし orz
てことで、サイトの磨き直しの方針は分かったけど、いつどうやるか全く未定。とりあえずメニューに「空き部屋」が2つもあるから、そこにそうゆーやつを書いてブチ込めるな。
まず「立体写真と日記」っつう、ちっとも関連性のないものが同居してるのをどうまとめるかで悩んでたりする。
アメリカでまた銃の乱射事件があったね。この理不尽な事件でお亡くなりになった方々に、哀悼の意を表します。
で、またしても学校。過去最悪の事件だそうで、コロンバイン高校銃乱射事件での反省と再発防止策が機能してないことが露呈してしまった。IT バブルの頃に、アメリカの証券取引所で乱射事件が発生したこともあったよね。こんな事件がアメリカで起こるたびに、現地の人には申し訳ないけど、「日本に住んでて良かった」と思いますなぁ。日本で銃を撃つ民間人なんて暴力団くらいなもんで、一応、一般人に迷惑がかからないようにやってるみたいだし、撃つにしても大抵は(ニュースで知る限り)、敵方の家に威嚇で撃ち込むだけみたいだし(と思ってたら長崎市長が何者かに撃たれた(汗))。
日本でも附属池田小事件という悲惨な事件もあったけど、銃じゃないだけ再発防止対策が比較的ラクだよね(まぁ凶器に使われたのが包丁だから、流通・所持を禁止にできないっつう難しさがあるけど)。同じような犯人にはサスマタが有効だってんで、今じゃ多くの学校でサスマタを常備してるらしい。でもさすがに銃弾に対してはサスマタじゃどうしようもない。つくづく日本って安全だなぁなんて。
銃社会といわれるアメリカはそれだけ銃に対する愛着が強いってことなんだろうけど、しかしほんと、ここまでの事件が起きてしまっても、それでもまだ銃を手放せないんだろうなぁ。チャールトン・ヘストン率いる全米ライフル協会(NRA)ってすごい政治力を誇ってるらしいし。
アメリカ社会って、自分の社会全体を変える力を持ってるはずなんだけどなぁ。セクハラという概念を作り出して国内で定着させて、さらにそれを世界中に広めるのにも成功した実績を持ってるってのに、銃規制に関してはどうも保守派が強くて、革新派は旗色が悪い感じ。
銃に対しては、アクション映画のスクリーン上以外じゃ何の愛着も持たないおいらとしては、まったく理解に苦しむ現実ですなぁ。たぶんアメリカ以外の多くの国の人が同じ感覚で今アメリカを見つめてるんだろうけど、アメリカって国は外国の目を気にしない国でもあるしなぁ。自力でどうにかしてくれとしか言えないのがもどかしい。
理解できないアメリカの慣習といえば、メートル法をいまだに導入できないでいるってのも不思議。いろんな意味で世界の中心でありながら、世界の人たちとスムーズに意思の疎通をしようって気持ちが感じられないんすけど。
亡くなられた長崎市長に、心からご冥福をお祈り申し上げます。なんだかんだ言って、銃に関しては安全だと思ってた我が日本も、うかうか安心してられなくなりましたなぁ。嫌な世の中になったもんです。
こんなときは逆に、趣味っぽいニュースでもネタにしましょうか。ということで、最近ちょっとおいらの趣味のツボにハマった、「DMV(デュアル・モード・ビークル)」の紹介でも。
そんで DMV とは何ぞや? とりあえず朝日新聞の特集記事を見とくんなまし。線路と道路、どっちも走れるオモシロ車両のこと。現在、試験的営業運転を実施中。人気は上々だそうで。開発した JR 北海道の DMV 紹介サイトはこちら。メリット・デメリットなど客観的な詳細情報は Wikipedia でどーぞ。
ほほう、線路上でも道路上でも、動力は同じタイヤを使うのか。ここがポイントだね。なるほどこれなら機構が単純になる。こういう単純化の発想ってのは大事なもんだ。この単純化をうまく発想できるかどうか、そしてきちんとモノにできるかどうかが、その全体構想を実用化(商用化)できるかどうかの重大な分かれ目になるんですな。JR 北海道は見事にそれをやってのけた。ふむふむ線路走行時の重量配分がカギでしたか。できたものを見るだけなら理解は簡単だけど、そりゃあ気を遣いますわな。おいらでもそのくらいは分かる。
で、面白いには面白いんだけど、運用における具体的なメリットがよく分からんのですが。Wikipedia の「メリット」を読んでも、どうにもピンとこない。つうか「デメリット」の方がずっと多いし説得力があるように思えるのですが。それを押し切ってまで開発・運用する JR 北海道の意図はというと、紹介サイトからすると、「低コストでの運用が可能」ってメリットでの一点突破らしい。んむーこれは、1両編成でもまだ客席が余ってしまう末端の路線に対応するってことですかね。定員わずか17名らしいし。
営業方針としては、線路のない集落をバスとして回って集客して、線路に乗っかってからは渋滞知らずで都市部に直接乗り入れ、という作戦かな? これだとコスト削減うんぬん以上に、乗客にとっての利便性を良くするという、企業の存在意義に直結した目的を叶えることになる。なんかそのあたりの説明が全くないんでよく分からんけど、まぁそういうことかなぁと憶測。
とりあえずメカとして面白いのが買いだけど、やっぱもっと具体的な「導入の動機」を知りたいところですなぁ。世界初の乗り物の開発までしたんだから、JR 北海道もそれなりの目論見があってのことだと思うんだが、その肝心なところがどうも見えてこない。
新聞社さんも、面白いマシンが世の中に出てきて浮かれるのは分かるけど、そこらへんもうちょっと大人に戻って、もっとツッコんだ取材をしてほしかったですなぁ。
萌え死に画像を拾ってきちゃった。あんましカワイイんで思わずくすねちまった。12匹……かな?
ここまでされると、「農家のオジサンととれたて野菜」に見えてきちゃいますなクスッw
つ〜かよく見たら一部合成じゃねーかこれ! 数え直したら本物は6匹だけか? 見事に騙された orz
アメリカの銃乱射事件についてはいろんなところで触れられてると思うけど、それに関連して、めちゃめちゃアレなブログを見つけてしまって。なんつーかこう、デムパみたいな(笑)。そこのブログランキングで1位になってるし。ていうか多分に政治的に偏った発言も多いんで、恐らく前々から知る人ぞ知る的なキョーレツブログだったんじゃないかと思う。
ここじゃそこにリンクも貼らないし URL も書かない。もう二度とアクセスしたくないし、皆さんに紹介もしたくないんで。その人、頭は良さそうなんだけど、ものの見方がゴリゴリに凝り固まっちゃっててさ。自分の主張を前面に出す姿勢自体も、別に好きにすればいいんだけど、その前に「自分は正しい。なぜなら自分は正しいから」の論理に陥ってるんだわ。
それと、誰かに植え付けられた考え方と自分のオリジナルの考えの区別がついてない。だから本人は自分独自の意見を主張してるつもりでも、実は他の人の操り人形になってしまってる。いやぁ自分を顧みるのにいい反面教師だわ〜。
こういう人には何を言っても無駄。ただ受け流すのが一番。この人は最近まで学生で、職に就いたばかりというからまだお若いらしいんだけど、いつか自分でその間違いに気付くことがあればいいですなぁ。自分の心の拠り所にしているものが意外と頼りないものだったとか、実は自分は拠り所に利用されてたとか、そこらへんを悟ってくれれば、そこからは話が早いと思うんだけど。さてこの人が自分の殻を破るのはいつの日のことでしょ。
ほんと勉強になりますこういう人の観察は。ブックマークに残さないからもうこれっきりネット上で出会うこともないだろうけど、この人の成長をお祈りいたしております。
話題のドキュメンタリー作品『不都合な真実』を観てきた。しかしあれだね、語られる地球環境の激変に関する内容のほとんどは、どこかで読んだような観たようなことが多くて特に目新しさは感じなかったんだけど(アメリカの大衆はそんなことも知らんのか……)、主演のアル・ゴア氏、彼の真摯な姿勢と行動力に感銘を受けたよ。おいらもあのくらい打ち込める何かが欲しいぞなもし。
で、ついでにというかどっちがついでか分からんけど、おいらの原稿が載ってる『八戸フォーラム かわら版96号』をゲットしてきた。
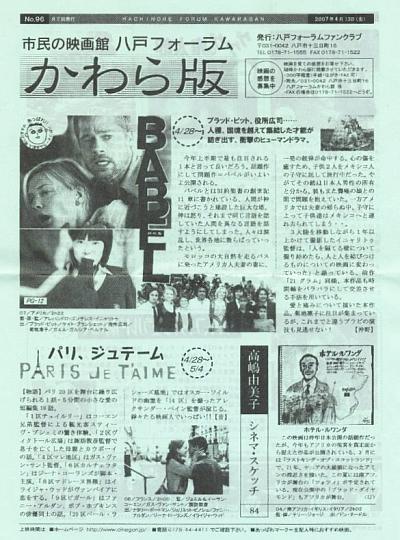
もちろん『ゲゲゲの鬼太郎』のレビューですがな〜。今回は裏面の上段真ん中に乗ってた。うむ、やっぱタイトルロゴと写真と作品データが付くだけで、説得力がめちゃめちゃゲタ履いてる。鬼太郎なだけに。♪カラーンコローンカランカランコロン……。
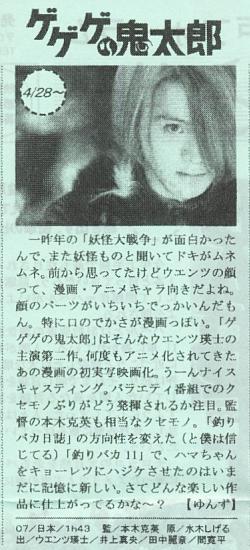
でもまぁ前回の蟲師レビューと同様、書いてる内容はかなりテキトーだったりする。ていうか今回の方がよっぽどテキトー (^^;) いやあのつまり、テキトーに見えるようにがんばったんですよ、ええ (^^;;) いやいや実際、おいらこのオファーを受けるまで、ウエンツ瑛士って知らんかったんだから。テレビ見ないもんだから。おいらなりに一生懸命ウエンツを調査して、ようやく書き上げたのよこの原稿(つまり「前から思ってたけどウエンツの顔って」「バラエティ番組でのクセモノぶりが」ってのは創作なのねw)。
でもさ、今回は監督が信頼できる人だから、そこは自分に嘘をつくようなことはしなくてもよかったよ。つうか『蟲師』ってまだ上映中なんだねぇ。八戸フォーラムのタイムテーブルには現時点で、「27日(金)終了予定」って書いてあるし、レイトショーが組んである。「終了予定」っつう曖昧な書き方をしてるってことは、そして公開からまる1カ月も経つのにレイトに入ってるということは、今でもそれなりに客が入ってるヒット作ってことですな。
んむー、おいら的には前に書いた通り大したことなかった映画なんだが、これはつまり宣伝戦略が成功した、と受け取ってもよろしそうですな。映画って興行だからさ、ある作品に人気が出るかどうかは、ひとえに宣伝がどれだけうまくいくかにかかってるわけですよ。内容如何に関わらず。で、作品的にダメな作品を商品としてどれだけ売るかってのは、封切り直後から発生する口コミをどう封じるかにかかってくるわけですよ。
『蟲師』がどういう宣伝戦略をしたかは分からんけど、あの内容なのにここまで興行を引っ張ってきたということは、宣伝戦略に成功したという以外考えられないんすよ。例えば事前宣伝で大々的に洗脳しちゃうと、洗脳された側は現実の作品を観た後、何かしら疑問に思いながらも「そんなはずはない。これは確かに面白い作品なんだから、自分がどこか見方を間違えたんだろう」なんてかなりお人好しな解釈をしてしまうんですな。
おいらもそれでかなり洗脳されてきたクチだからなぁ(笑)。とりあえず『敦煌』(1988)ね。もう観る何カ月も前から「これは面白いはずだ」と信じ切ってた。この状態おかしいよね。まぁでも観たら期待通りの作品だったんで文句はなかったんだけど、それで『自分には映画を事前に見極める目がある』との勘違いを起こさせた罪な作品でもあった(先に『ロボコップ』(1987)でも同じ体験をしてたのが、勘違いに拍車をかけることになった)。その調子で事前にピーンと来てしまったのが『いつかギラギラする日』(1992)。
実際に観に行ったらさ、映画館から出るときなんかこう、キツネにつままれたよーな気分だったよ。でも「面白くなかったのはおいらの見当違いなんだ。面白いはずなんだこれは」ととっさに自分を騙すあたり、完全に宣伝戦略に呑まれてたんだな。で、やっぱ心のモヤモヤが晴れなくて、もういっぺん観に行ってはっきりしたんだ。「この映画はクズだ」と。「おいらは宣伝に踊らされてた」と。
ちうことで、映画ってのは実際に観てみるまでは、面白いかどうか分からんのですよ。特に映画の公開前レビューとか試写会情報とかには気をつけた方がいい。公開前に悪いことを言うと営業妨害になってしまうからね。レビューを出す人はみんな映画好きだから、どの映画も興行をがんばってもらいたい。だからみんなそこらへんは仕手側に気を遣って、悪いことは言わないようにしてるんだよ。
例えば今回の原稿を書かせてもらった かわら版 ってのはぶっちゃけ八戸フォーラムの宣伝媒体なんだから、これから八戸フォーラムで上映する作品について悪く書くわけがない(まだ観てもいないんだから悪く書けるわけがないっつうのもあるけど)。だから、『蟲師』みたいにおいらの好みじゃない監督の作品を紹介するってことになっても、自然と期待感を煽るような書き方になっちゃうんですよ。だって宣伝だもん(開き直り)。
てなわけで、おいらの書いた かわら版 の原稿に関しては、本音はこの日記で言わしてもらうことにいたしますです。既に『蟲師』についても『ゲゲゲの鬼太郎』についても、レビュー執筆時点での本音をここに書いたけどね。まぁさっきから言ってるように、執筆時点じゃまだ作品を観てないわけだから、その「本音」で言ってることも全然お門違いの可能性があるっす。その点もご了承くださいませ。
『サンシャイン2057』を観てきた。久々のハード SF 映画っぽかんったんでワクワクドキドキ。ちなみに内容はほとんど知らないまんま。知ってたのは、弱ってしまった太陽活動を再び活性化させるために、太陽に核爆弾を撃ち込むという設定と、その宇宙船の船長が真田広之だってことくらい。真田広之もワールドワイドに活躍するようになったねぇ。イギリスでの舞台仕事の経験があるらしいから、英語が渡辺謙よりずっとうまかった(そういや真田君、せっかく『ラストサムライ』に出てたのに英語を喋るチャンスがなかったよね)
その割に死ぬの早すぎるぞ真田! せっかく船長という大役を射止めたのに、話が本格的に転がり出す前にあっけなく死んじゃうんだもんなぁ。正直、日本人としてがっかりだったよ。真田演じるカネダ船長を皮切りに登場人物がどんどん死んでいくんだけど、やっぱしというか結局最後は白人だけが生き残るんですな。
有色人種はカネダ船長の他に、死ぬ順に、東洋人男性の航海士(航宙士? 自殺)、南米出身っぽい黒人男性が一人(乗り移った先の宇宙船に置き去り)、東洋人女性の植物学者(ミシェル・ヨー 悪役に刺殺される)。で、邪魔者はいなくなりましたよとばかりに、そこから先のおいしいところは白人だけで展開しちゃう。なんだかなぁ。そのたびに親近度がどんどん遠ざかってしまってさ、どうせなら普通のハリウッド映画並みに、はじめから東洋人抜きでやってくれた方がよっぽど話に入り込めたんじゃないかとか。
でもまぁ「おいしいところ」と言ったって、ハリウッドお得意の(つまり見飽きた)密室スリラーなんだけどさ。このベタな展開にもドン引きしてしまったよ。で、追っかけ役の怪人さんが登場する場面じゃなんだかよく分からない映像処理をして、何やってるんだかよく見えないし、怪人さんが計画を妨害する理屈もよく分からんまんま。実は失敗した前ミッションの船長さんがミッション遂行中に何らかの啓示を覚えて怪人化したんだけど、なんか単に、重大ミッションのプレッシャーに負けてクルクルパーになってしまったという解釈で十分な気がする。
そのくらい、悪役の論理の説明が足りなかった。それがこの映画の限界を指し示してたなぁ。映像が素晴らしかっただけに、ものすごく惜しい。こいつはもう映画史に埋もれてしまう運命ですな。映像表現以外にあんまり志の高さを感じさせなかったよ。
その映像表現だけど、太陽を横切る水星のシルエットが印象的だったなぁ。いまや CG はあんな芸当までできるようになったのか。『スペースカウボーイ』(2000)を観て以来、これからの SFX は「何ができるか」なんてのは当たり前で、「何をどう表現するか」という芸術分野に足を踏み入れつつあると感じたもんだけど、その直感は間違ってなかった。その意味では今回の『サンシャイン2057』は、成功したと言っていいと思う。そんじょそこらの CG 屋さんじゃできない発想&技術の、見事な「水星の太陽面通過」でございました。天晴。
けんど、ハード SF とはいえ、さすがに設定に無理があった気がしたよ。直径が地球の109倍もある太陽。表面温度は6000℃。活動が弱まってるとしても4000℃以下ってことはないでしょう。そんな途方もない、文字通り天文学的な物体に、たかだかマンハッタン島程度のサイズの(ていうか地球ごときの資源から作った)核爆弾を打ち込んだところで、一瞬でお天道さんのご機嫌が変わってしまうとは思えないのが痛いところだったかな〜。そもそも太陽表面から放射されるエネルギーってのは、中心部の核融合から発生した電磁波が何万年もかけて表面にしみ出してきたもの。だから刺激を与えるんなら中心部に与えなきゃ話にならない(さらに言えば、今からたった50年以内でそんなに太陽活動が激変するとも思えない)。
太陽は表面の温度が一番低くて、内部に行くほど温度が高くなってる。でも表面温度はいきなり数千℃。核弾頭を中心部近くにまで安全に届けてから爆発させるなんてどだい無理。核爆弾の起爆装置なんか表面で融けちゃうよ。相手はデススターじゃないんだから。表面近くで爆発させるにしても、その程度の爆発なら普通に太陽表面で起こってるから、いくら太陽活動が弱ってるとはいえ、太陽活動そのものを刺激させるほどのことにはならないはず。
それを言っちゃあこの話そのものが成り立たないんだけどさ。これは今から50年後の未来を想定してるらしいけど、おいら的には、今から50年経っても、太陽活動を人為的に操作するなんて無理だと思う。それよりだったら、太陽活動の衰退に合わせて地球の軌道をもっと内側にずらして、もっと太陽に近づける方がまだ現実的だと思うぞ(これも50年じゃ無理っぽいけど)。まぁそうなると1年がグッと短くなるわけで、四季の変化が変調を来すわけで、生態系が狂ってしまうけどね。
それよりだったら、ガンダムみたいに巨大スペースコロニーを地球の衛星軌道上にたくさん作って、そこに動植物もまとめてみんな移住したらどうだ。地球の公転軌道を変えるよりは実現性が高い気がするが。でもやっぱり実現性で言えば難しいものがあるな。
だったらだったら、太陽光を反射する巨大な鏡衛星を多数打ち上げて、地球を照射するってのでどうだ。なんかこれが一番、技術的にも環境的にも妥当な気がするが。
つうか、昨日『不都合な真実』を観たばっかりなんで、太陽活動が弱まって地球が凍る心配より、CO2 による地球温暖化の方を心配すべきなんじゃないのかねぇとか思ったり。アメリカってやっぱ温暖化に対する危機感薄いよね。
どうも『太陽の危機』を描いた SF 作品ってスネに傷持つやつが多いな。『クライシス2050』 (1990) ってバブル映画もあった。日本の企業が金を出して、今よりずっと質が低かった日本の映画人がアメリカに作らせたニセハリウッド映画ね。おお、allcinema でも酷評だなぁ。そうかそうか監督名義が「アラン・スミシー」だったのか。これじゃあなぁ(苦笑)。いやビデオで実際に観たけど、なんか凄まじくつまんない映画だったよ。ははぁ、こっちは『サンシャイン2057』とは逆に、太陽活動が活発になりすぎて困っちゃったって設定だったのか。もう完全に忘却の彼方だったわいな。
覚えてるもう1本は、『さよならジュピター』(1984)。こっちの設定は、太陽にブラックホールがピンポイントでぶつかってしまうから困ったぞ、という設定(一番あり得ない設定だと思う)。時代設定は22世紀なんだから、ドラえもんに頼めばヒラリマントか何かでどうにかしてくれそうな気もしたけど、ヒラリマントの代わりに木星をブラックホールにぶつけるというアイディアでどうにかするっつう話だった。
しかし最近知ったんだけど、木星って文字通り盾になって、小惑星(巨大隕石)から地球を守ってくれてるらしい。んで、木星がないと地球に小惑星が落ちてくる確率が1000倍になるんだそうで。Wikipedia によると、「直径1kmほどの小惑星の地球への衝突は100万年に数回」とのこと。これが1000年に数回になっちゃうってことですかい? つまり何百年かに1回。『さよならジュピター』での世界って、最悪の事態を回避したらしたで、未来人も大変ですなぁこりゃ。太陽が通りすがりのブラックホールに吸い込まれてしまうよりはましだけど。
しかしまーこの作品、かなり鼻で笑われる対象になってるんだけど(実際そういう出来映えだしね)、でもおいら、あの独特なヴィジュアルが何とも言えず好みなのよね〜。ミニチュアがミニチュアらしくて、その精一杯加減がすごく可愛くて。今どきの何でも精密に再現できちゃう CG じゃああのワビサビは出せんでしょう。てことでおいら、この映画の悪い部分はみんな目をつぶって(ほとんどの部分に目をつぶることになるんだが)、隠れ切支丹的にあの作品のファンなのよね。でもそれ言うとほんとに鼻で笑われちゃうから、蚊の鳴くようなちいちゃい声で「ちゅき」としか言えんのがもどかしいのじゃよ〜。
ちなみにあの映画に出てきたオタクっぽい白人の少年(マーク・パンソナ)はその後、モデルとして一時期活躍した後、小室哲哉の GLOBE のメンバーのマーク・パンサーとして芸能界に再デビューしたんだが、彼のその映画デビューの過去は触れちゃいけない秘密っぽい。ていうかマーク君、今どうしてるんだろ。
お、Wikipedia に詳しく載ってた。Wikipedia すごすぎ (^_^;)
昨日、八戸の市議会議員選挙があったんだわ。で、2位以下を大きく引き離してダントツでトップ当選したのが、無所属新人の女性候補(27歳)。なんでも史上最多の得票数だったそうで。その人の親父さんは元市議会議員で、この前の県議会議員選で落ちちゃったんだわ。4年前の県議会議員選と合わせて2期連続落選の親父さんを養うってことで、娘さんが市議会議員選に立候補したってことらしい。
でさ、この人の選挙ポスターの顔写真がこれまたすげぇカワイかったのよ(笑)。選挙事務所の看板もピンクだったしさ(殺風景なプレハブ小屋にピンクの大看板ってのも、場末っぽくてアレだったけど)、たぶん写真を何十枚も撮って、そのうち一番かわいく写ったやつを使ったんじゃないかと思うんだが、おいら的にはこのかわいさで大量の浮動票を獲得してトップ当選をもぎり取ったんじゃないかと踏んどるよ。もちろん親父さんの票田を受け継いだってのもあったろうけどさ。
一応、噂だけど証言もゲットした。なんでも選挙の期間中、「ポスター下さい」と言う若い男が選挙事務所に複数現れたとのこと。だってほんとカワイイんだもんなぁポスターの写真。実物はどうか知らんけど。
なんだかなぁ。こんな、アイドルの人気投票みたいな結果出しちゃって、そんな選挙でいいと思ってんのか、そんな動機で投票したお前ら! かく言うおいらはどうだったかっつーと、県議会議員選のときと同じく、親戚に頼まれた候補をそのまんま書いて出しちゃった。そんな選挙でいいのか>自分 orz
mixi のマイミクさんが紹介してくれたページにツッコミ入れてみる日。
NIKKEI プラス1の『夫に言われて傷ついた一言』ランキング表。そして解説。なんかもういろいろ言いたいことがやまやま。とりあえずいつ消されるか分からん記事なんで、ランキング表だけでもコピペしとこう。
| 1 | 「君も太ったね」 403 |
| 2 | 体調が悪いのに「ごはんはないの?」 318 |
| 3 | 「家にいるんだからヒマだろ」 260 |
| 4 | 「片づけが下手だ」 218 |
| 5 | 育児など手伝ってほしいといったら「仕事で疲れているんだ」 201 |
| 6 | 「うるさい」 184 |
| 7 | 話し方について「しつこいな」 176 |
| 8 | 「誰のおかげで生活できているんだ」 163 |
| 9 | 「で、結論はなに?」 145 |
| 10 | 「おれの金を自由に使って何が悪い」 139 |
| 11 | 「君には関係ない」 100 |
| 12 | 子供の素行の悪さについて「お前に似たんじゃないのか」 95 |
| 13 | 「もっと効率よくやれば」 92 |
| 14 | 子供のことを相談して「どうでもいいじゃないか」 80 |
| 15 | 「うちの親の悪口はいうな」 77 |
どーでもいーけど元の table ソース、めちゃめちゃ汚かったぞ。かなり昔の規格の HTML 使ってやがるくせに(今どきタグを大文字で書くなよな〜だっせ〜)、いっちょまえにスタイルシート組んでやがった。th タグの使い方もなんだかおかしいし、改行の入れ方も中途半端。よっぽど変テコな HTML エディタ使ってんだろぉなぁ。面白半分に Another HTML-lint gateway で添削したら、「がんばりましょう このHTMLは -71点です」だそうで。マイナスだぞ。大丈夫か日経。上に書いたやつはそこらへん全部直しといたよ。手書き HTML の参考にドーゾ(笑)
ちなみにこのページの点数は現時点で「よくできました このHTMLは 92点です」だ。もちろん慌てて修正した後だw 修正前は「ふつうです このHTMLは 40点です」だったけど。ていうかそのおかげで日記ページ自動生成 JavaScript に不具合を発見して、去年の9月以降の日記ページ全部修正したよ。去年の8月末、一体何考えてあんな変なスクリプト書き足したんだろ(謎)
それはいいとして本題に入りますか。とりあえず、「2. 体調が悪いのに『ごはんはないの?』」「3. 家にいるんだからヒマだろ」「4. 片づけが下手だ」「8. 誰のおかげで生活できているんだ」「10. おれの金を自由に使って何が悪い」「12. 子供の素行の悪さについて『お前に似たんじゃないのか』」「13. もっと効率よくやれば」……以上7つはもう問題外。完全にアウトですな。それを言って奥さんがどう感じるかを全く考え及ばない、想像力の乏しい男性または、悪い意味で昔気質の亭主関白クンですなぁ。「10. おれの金を自由に使って何が悪い」は、婚約前のカップルに限ってはちょっと有効そうな気がするけど、婚約後や結婚後はダメでしょうやっぱし。
体調が悪い奥さんが料理を作るのについては、伊丹十三監督の『タンポポ』(1985)で感動的なエピソードが挿入されてたのを思い出したよ。小さなアパートで暮らす、裕福とは言えない一家。妻であり母親である女性は床に臥せっていて、夫と子供たち、そしてお医者さんが彼女の周りを囲んでる。どうやら病気で臨終間近らしい。旦那は必死で呼びかける「しっかりしろ! お前が死んじまったらオレたちはどうなる!」。そこで旦那はふと思いつく。「そうだ! 母ちゃんメシ作ってくれ! メシ!」。すると妻はふらりと立ち上がって台所に行き、チャーハンを作る。「できたよ〜」とチャーハンを中華鍋ごとちゃぶ台に置くと、夫と子供たちはよそって食べ始める。「うまい、うまいよ母ちゃん」の言葉に満足げな表所を見せた妻はゆっくりと倒れ込む。医者が脈を取り、「ご臨終です。○時×分でした」。夫は子供たちに叫ぶ。「食えーッ!」。
あああ、思い出したら泣けてきた (T□T;) 母親のあんな後ろ姿を目撃した子供たちは、きっと立派な大人に育ったことだろう。一流の料理人として大成してるかもしれんなぁ。
また話がずれちった (-▽-;) 戻して、と。「5. 育児など手伝ってほしいといったら『仕事で疲れているんだ』」「6. うるさい」「7. 話し方について『しつこいな』」「14. 子供のことを相談して『どうでもいいじゃないか』」……以上4つは、旦那さんがきつい仕事から帰った直後とかで、心身共にマジでヘロヘロな時ってのが想像できる。あとはもうメシ食って風呂入って寝ることしか考えられないズタボロ状態。こうゆーときは、旦那の側から先にヘロヘロサインを出して「今日は構わないでくれ」ってのを示した方がよさそう。奥さんもそれを分かってあげるといいけど、奥さんの側もそれなりの理由があって話しかけてるんだから、そうなったらなったで、旦那の側としても最後の力を振り絞って、できる限り優しく接してあげなきゃいかんだろうなぁ。まぁその努力の結果が「うるさい」「しつこいな」なのかもしれんけど。
でもこれ旦那がピンピンしてる状態で言われたら、奥さん傷つくの通り越してマジでムカつくだろうなぁ。
「15. うちの親の悪口はいうな」。これはどうなんだろ。おいら未婚だからよく分からん。誰だって親の悪口を言われたら腹が立つもんだと思うが、言った人が傷ついたってことは、悪口のつもりじゃなかったと推察できる。舅・姑の嫁に対する態度が悪過ぎて、耐えに耐えてきた奥さんとうとう我慢できなくて、間に立つ旦那さんに窮状を説明しようとしたときの返事かと思われ。それが旦那にとっては親の悪口に聞こえたんだと思われ。これは旦那が状況を把握できてないってことですな。理想を言えば、こんなとき旦那さんは奥さんの側に立つべきかと。
チャップリンの『サーカス』(1928)のラスト近くで、ちょっと似た場面がある。自分の娘(空中ブランコ担当)をいじめる悪い父親(サーカスの団長)に対して、その娘と結婚したばかりの旦那(綱渡り担当)が、「私の妻に手を上げるのは許さない!」と毅然とした態度で臨むんですな。嫁の父親という状況は違うけど、親に対して、また上司に対してそういう態度で妻を守るその姿においらは感激したもんさ。世の旦那さんがた、ここはひとつ『サーカス』を観て、漢の生き様を学んでみてはいかがでしょう。主人公チャーリー(クラウンと綱渡り代理担当)の決断と行動も、ヲトコ心に突き刺さること請け合いですぞ。
ていうかこの映画、憶測だけど『男はつらいよ』の原型になったと思うんだよね。多感な思春期にそんな寅さんっぽいチャーリーの姿に胸を打たれ、今もときどき DVD を見返しては涙するおいらがいまだに結婚できないでいるっての、感化され過ぎなのかねぇ(溜息)
ちょっと意外だったのが「1. 君も太ったね」。んー、そんなにも気にするものだったのか。気をつけてるつもりだったが、これからは女性と話をするときは、以前にも増して気をつけることにしよう。ていうかおいらの場合これを言った瞬間「あんたは前から太ってるよね」と返されて一発轟沈が目に見えてる。やっぱ言わぬが花。
「11. 君には関係ない」は、状況がよく分からないんで、立ち入ったコメントはできんな。冷たく言われたとしても、もしかしたら奥さんを巻き込みたくない難事かやましいことを、旦那さんが抱えてしまってるのかも。やましいことは論外として、もし難事だったら、それは奥さんが旦那さんに守られてるってことで、ある意味奥さんは幸せなのかもしれんな。けどこれだけは言える。結婚式で「苦しいときも、悩めるときも」と、何事も2人で解決することを誓った以上、奥さんを仲間外れにするのは分が悪いですな。片意地張らないで、率直に奥さんに相談しても罰は当たらないと思うぞ。
ていうかこれも、夫婦の問題っつうより、人としての礼儀の問題だと思うが。親しくしてきたはずの友達に「おめーにゃ関係ねーよ」と突き放されたらどう感じるよ。そこらへん想像力を働かして、相手が夫であれ妻であれ、とにかくこの呪われた言葉を相手に言わんようにするべきな気がする。人として。
最後に残ったのが、「9. で、結論はなに?」。これについては解説ページが「6. うるさい」「7. しつこいな」とまとめて「男性は報告や結論を求めて話すが、女性は過程に重点を置くので結論はなくてもよいことが多い。それを理解せずに夫が話を遮ると妻は不満を感じる」としてるけど、そんなもっともらしいことじゃなく、もっと単純なことじゃないですかね。
旦那さん、延々と聞かされてる話の内容や演出がつまんなくてつまんなくて、うんざりでうんざりで、飽きてるだけだろ。話しかたが下手なのが悪いんだろ。男だから女だから以前のことだろ。オチがなくても面白くすれば解決と。
こうして見ると、「夫に言われて傷ついた一言」ってのは、性別の違いによる行き違いって部分も確かにあるけど、基本的には、人と人との間にあってしかるべき礼儀というか気遣いというかが欠乏したときに発生するものらしいですな。おいらは結婚のご予定などこれっぱかりもございません状態だけど、いつでも思い出せるように、ここに記録しとくことにするよ。まぁ思い出しても探すのに苦労しそうだけど (-▽^;) ピクピク
八戸フォーラムかわら版の原稿依頼2本受けてきたよ〜。まずはあの『大日本人』。300字。締切は5月21日。「あの『大日本人』」っていうかさ、松本人志初監督作品で6月2日公開っつうデータ以外、現時点でおいら何も知らないんですが(汗)。元締めさんに「これ大丈夫ですか?」と一応訊かれたんだけどさ、そう言われたら「大丈夫です。やってみます」と答えるしかないでしょう漢としては!! まぁ公式サイトとか見てぼちぼち書くことにしますわ。
今 Wikipedia に当たってみたけど、作品自体に対する大した収穫なし。しかし、竹内力、神木隆之介、UA、板尾創路とはまた豪華なキャストですなぁ。けどどう書いていいか全く分からん。暗中模索以前の状態。どうしよう。安請合いしちまったかなぁ……。
もう1本は、かわら版DX(デラックス)の『この監督に首ったけ』。1000字。締切は6月15日。3人の監督に関するコメントのうちのひとつを担当することになった。条件は日本人監督。てことで、ベタかなぁと思ったけど、黒澤明でいくことに決めちゃった。いまだかつて誰も成したことがない(と思われる)独自の切り口から、黒澤監督を紹介しようかな、と。
問題は字数。1000字ってのはまだやったことがない。いつもの3倍ちょっと。まぁ書いていけば自然に埋まると思うんだけど、その長さでどうバランスを取るかに苦労しそう。とにかくやってみるしかないですな。締切まで日があるしネタもあるってことで、『大日本人』よりは簡単に済みそうな気がする(笑)
『ゲゲゲの鬼太郎』の原稿、けっこうウケたっぽい感じ (^_^;) まぁこうゆー、作品内容に根ざさないふざけた作品紹介もアリかなってことでひとつ。
「将来、電気自動車にはクラクションの代わりにチャイムが付くことになるだろう」。
というのを昔、何かで読んだことがある。電気自動車はエンジン音がなく静かだから、歩行者の後ろから近づいても歩行者が気付かないだろう。そこでいきなりクラクションを鳴らされると歩行者はびっくりするだろうから、優しい音色のチャイムが採用される可能性がある、とのことだった。
チャイム、要らないよね。現行のガソリン高級車のエンジン音は、ほとんど無音の域にまで達してる。でもクラクションに代わってチャイムを採用なんて話、聞いたことがない。歩行者がびっくりするかどうかは、クラクションの鳴らし方にもよるしね。
乗用車に装備されてるクラクションの音は大抵、クレッシェンド気味に鳴り始めるようになってる。だから一瞬だけ鳴らすと、音が全開になる前に止まって、「クン」て感じの上品な音になる。前を歩く歩行者に自分の存在を気付かせるためには、これで充分。
商用車なんかのクラクションはいきなり全開のブザーなんだけど(こっちの方がコストが安いんだと思う)、こういう状況でも問題なし。なぜならエンジン音がうるさいから(笑)気付いてもらえる。商用車が電動化して静かになってしまったらどうなるかっつうと、チャイムよりは乗用車用クラクションの方が安そうなんで、やっぱしチャイムの出番はなさそう。
まぁあと、ヨーロッパの CO2 削減トレンドとして、ディーゼルエンジンを乗用車に使うって流れが日本にも来てるみたいだけど、ディーゼルの音も昔よりだいぶ静かになったとはいえ、相変わらずダララララララとスペイン人みたいな巻き舌な音を出してる。あの音がある限り、やっぱしチャイムの出番はないんですなぁ。
クルマにチャイム、きっと思いついたときは、その人にとっては素晴らしいアイディアに思えたんだろなぁ。
そんじゃクルマに関する話題もういっちょ。エタノール混合ガソリンについて。
今日からバイオガソリンというのが試験販売されることになった(記事)。エタノール混合ガソリンなんだけど、環境省が推進してる直接混合方式じゃなく、まずエタノールとイソブチレンを化合させた ETBE(エチルターシャリーブチルエーテル)っつう物質を作って、これをガソリンに 7% 混ぜるんだそうだ。そうするとガソリンにエタノールが 3% 混ざった「E3」という規格と同等になるそうで。
なんでこんな直接混合に比べてめんどっちいことするのかっつうと、石油連盟の資料(PDF)によると、
だそうだ。資料を読むと、そ〜か〜直接混合いいじゃんなんて簡単に考えてたけど、いろいろ問題があるんだな〜。石油業界については 2007.4.3 でひどいこと書いちゃったな。どうもすみませんでした m(_ _)m しかしだね、資料じゃ「現行の品質確保法上では、ガソリンの含酸素率の上限値が 1.3% となっていることから、ETBE では 7% 程度まで混入可能と見られる」ということで、混合割合は直接混合方式で言う E3(エタノール 3% 混合ガソリン)が限度ってことらしい。ところが世界じゃ「E5」「E25」なんつう規格も出来上がって、地球環境改善に向かって邁進してるわけだ。
ていうかアメリカじゃもう普通に E10 燃料が出回ってるそうだ。おい石油業界! 直接混合は問題あるんじゃなかったのか!?
それはそれとして、とうとう国内で販売された ETBE について考えよう。日本じゃ法律の縛りで「ETBE の上限: 7%」が決まってしまってるってことで、ここらへんの規制が緩和されれば、もっと ETBE の比率を上げられそうですなぁ。まぁ原料のバイオエタノールの安定供給が前提だけど、環境省は E5 とか E10 とかそれ以上を狙ってるらしいから、規制緩和ももうすぐかと思われ。
つうか、将来的に燃料電池自動車が普及するだろうってことを考えると、いずれはバイオエタノール 100% 燃料が必要になってくるはず。ていうかそうなってくれないとゼロエミッションが達成できなくて環境負荷が増える一方だし、世界中の油田も早いうちに枯れてしまう(北海油田が既にほぼ枯れたらしい)。北極圏・南極圏の氷が溶けて世界中の平野部(つまり都市部)が水浸しになったり、太平洋上のサンゴ礁でできた(海抜高度が平均数メートルしかない)島国が水没して消滅したり、中近東のオイルマネーで豊かに暮らしてる国々が、油田発見以前の極貧な暮らしに逆戻りしたり。
『不都合な真実』じゃないけど、こうなっちゃったらまずいでしょう。おいらの地元で言えば、八戸の市街地は高台にあるんで難を逃れられると思うけど、おいらの家は海抜ゼロメートル地帯にあるんだわ。他人事じゃないんですよ実際。
んでまぁ日記が遅れ気味なんで、続きは次回の講釈にて。
ETBE のもうひとつの材料であるイソブチレン(イソブテン)は、何を原料にしてどう作られるのか疑問に思った。事によっては、かなりのエネルギーを消費する、実は環境負荷が高い製法なんじゃないのかとか。
Wikipedia に載ってた。ふむふむ、「接触分解によるエチレン、プロピレン、改質ガソリン製造の副産物として生産される」のか。「接触分解」ってのは、触媒による分解だそうで。こうして見ると、化石燃料由来の物質とはいえ、製造工程での環境負荷はあんまし高くなさそう。
つうことで、ETBE(エチルターシャリーブチルエーテル)混合ガソリンは、時代の徒花としていずれ消える運命にあると思う。本命はバイオエタノール 100% 燃料を使った燃料電池自動車または、その燃料に対応したエンジン式の自動車(BMW は違う未来 [液体水素を燃料とした自動車社会] を描いてるけど、それが笑止なのは以前書いた通り)。
昨日も紹介した石油連盟の資料(PDF)によると、「エタノールの熱量はガソリンよりも3割程度少ないため燃費が悪化」とあるけど、エタノールはガソリンよりオクタン価が高いため、エンジンの圧縮率をより上げられて高効率化が図れるっつう意見もある。エタノール専用エンジンの設計は間違いなくそこを狙うはずだから、ガソリン車より燃費が落ちるにしても、3割ってほどにはならない。
で、問題になってくるのが、バイオエタノールの安定供給。輸出できるほどの生産量があるのはブラジルだけ。日本での取り組みとしては、今まで捨てるしかなかった廃木材を特殊な菌で発酵させてバイオエタノールを作る、というやつ。確か大阪辺りで最近、プラントが実際に動き出したはず。おっ、過去の新聞記事にも似た内容のが出てる。
(2003.7.30 朝日新聞・抜粋) 月島機械のエタノール製造試験プラント(千葉県市川市)を訪ねた。最初の工程では、住宅解体などで出る廃木材を数センチの小片に砕いたものを、硫酸と圧力で糖に変える。次に特殊な菌と酵母菌で糖を2日間発酵。たまった黒い液を蒸留すれば、無色透明のエタノールが完成する。
ブラジルや米国ではすでに植物から大量のエタノールを製造している。ただし、材料はトウモロコシのデンプン、サトウキビのショ糖という本来食料に使われるもの。搾りかすや廃材など木質バイオマスは使わない。
その理由は、木質バイオマスの繊維成分の一つ、ヘミセルロースにある。同成分からできる糖を発酵させる菌が自然界にないからだ。
月島機械はヘミセルロースの糖を発酵させる遺伝子を組み込んだ大腸菌を使う。この菌は米国が開発した。酵母菌も使うのは、木質バイオマスのもうひとつの繊維成分、セルロースからできる糖を発酵させるためだ。
「木をまるごとエタノールにするプラントの商業化で、世界の先陣を切りたい」と三輪浩司・研究開発部長。9月に本格稼働する予定の試験プラントは、1日に廃材4トンを処理し、800リットル(材料重量の約15%)のエタノールを生産する。
これ、廃木材だけでなく間伐材や古紙なんかも有効利用できそうだね(古紙は相場が上がってるから、コスト面で難しいかもしれんけど)。しかしこれだけじゃ多分まだまだ足りない。もっと大量に生産できる手段が欲しい。高効率でバイオエタノールを生成できるサトウキビは、日本のかなり南の地方でないと生産できない。九州南部・沖縄あたりだけか。これじゃ日本全国に行き渡らせるのに全く足りない。
減反対象になった土地にトウモロコシを植えるのも手だけど、それでも足りるかどうか分からない。なんでも、ドイツ1カ国の自動車用エタノールを作るのには、ドイツ全土をトウモロコシ畑にしてもまだ足りないって話を聞いたことがある。日本も似たような状況かと。結局輸入に頼ることになるんだが、ここでひとつ提案したい。中東諸国でサトウキビを栽培してはどうか。
「そんな見渡す限りの砂漠の土地で、どうすりゃ植物が育つんだよ」。ごもっとも。しかし、砂漠地帯での農業は可能なのだよ。その代表がイスラエル生まれの「点滴栽培」(資料1, 資料2)。イスラエルもまた中東の砂漠地帯の国でありながら、ヨーロッパに農産物を輸出してる。イスラエルにできて他の中東諸国にできないはずがない。今は無駄に太陽エネルギーを吸収して大気に放出するがままの砂漠地帯で植物が育つ。暑い地域だけによく育ちそう。それだけで地球温暖化に対して幾分かの抵抗になる。さらにそれで作られたバイオエタノールを化石燃料に替わって使うことで、温暖化に歯止めをかけられる。
しかも、このままだといずれ石油が枯渇して、現地の人は昔の極貧生活に戻らざるを得ないのが目に見えてるけど、この新たなエネルギー産業を同じ土地で興すことで、それを防げる。いいことずくめじゃありませんか。
幸い、中東諸国と日本は、宗教の壁を越えてけっこう友好的に付き合ってる。理由としては、日本は日露戦争以来、それまで絶対的な存在だった白人国家群に戦争や経済で正面から食ってかかっていい勝負をしてきたという同情もあるけど(中東までは日本軍は進撃しなくて、現地で狼藉を働かなかったしね)、実利的な話、日本が大量の石油を買ってくれてるからってのが大きいと思う。
でもこのままじゃ、石油の切れ目が縁の切れ目。石油はいずれなくなる。中東諸国と日本はまた戦前と同じく、他人同士になってしまう。そうなる前にバイオエタノールの中東での大量生産を確立して、その国々には末永くエネルギー産出国家として君臨していただこう。
石油がいずれ枯渇するのは、現地の人たちも十分承知のはず。それに替わる産業を模索してるはず。そこで日本からバイオエタノール生産を持ちかけたらどうかね、という話。買う客がもう決まってるんだから、これほど確実なビジネスはない。
イスラム圏からの反発が予想されるイスラエル発の点滴栽培に限らなくても、意外と日本は砂漠での植物栽培の独自ノウハウを持ってる。鳥取大学が鳥取名物の砂丘を利用して、年々着々と成果を上げてる。例えば、紙おむつや生理用品としておなじみの、高分子吸収体を利用した農法ってのも開発済みだそうだ。
その土地その土地の気候や土の具合に合わせた最適な農法を開発・提供することで、日本は手助けできる。中東における日本の立場がまたまた良くなること請け合い。特に石油の枯渇以降、その有難味が現地で実感されることだろう。お互いに足りないもの(日本にとってはサトウキビ栽培に適した暑い気候、中東諸国にとっては農業技術と顧客)を補い合えば、これだけのことができるんだぞ、と。
日本の周辺は反日国家だらけで(ほとんど自業自得か言いがかりだけど)、これからも日本の外交は苦労することが予想されるけど、だからこそ日本の友達を多く作っておくことが大事なんじゃないですかね。しかも環境対策としておもっきし有効だし。
つうことで外務省さんと環境省さんと農水省さんと経済産業省の資源エネルギー庁さん、中東でのサトウキビ栽培構想、いかがでしょうかね。思い切ってイラクに持ちかけてみるとか。サマーワは失業率が 20% を超えてたそうだ。他の地域も似たようなもんかと思う。現地の失業対策としても歓迎されるんじゃないですかね。
ガソリン車だけバイオエタノールで排ガスがきれいになっても、ディーゼルの軽油もどうにかせんと片手落ちですな。実際、ガソリンよりディーゼルの方が CO2 を出してると思うんだ。台数じゃガソリンエンジンだろうけど、1台あたりの排気量じゃディーゼルでしょう。道路を走るクルマだけでなく、工事用の機械もそうだし、中型・大型船舶もディーゼル。こいつらが排出するガスがきれいになれば、地球環境はグッと良くなるはず。
で、聞き及んだ軽油の代替燃料が ジメチルエーテル。天ぷら油を使う BDF はまた後でね。
ほほう「低温で メタノール を硫酸で脱水すると得られる」ですか。けっこう簡単に製造できそうですなぁ。メタノールが原料とくれば、バイオエタノールよりも効率良く作れるかも。昨日と同じ記事から抜粋。
(2003.7.30 朝日新聞) 一方、メタノールでは昨年、三菱重工業などが長崎県に試験プラントを造った。発酵ではなくガス化合成法だが、材料は同じく廃木材や雑草などの木質バイオマス。
微粉砕した材料に酸素と水蒸気を加えて800から1千度で不完全燃焼させる。生じた水素と一酸化炭素のガスに銅、亜鉛系触媒を働かせるとメタノールができる。
生産効率はエタノールより高い。現在のプラントは1日240キロの廃木材などを処理し、その重量の20%相当のメタノールを生産する。規模を大きくすれば、50%の効率も到達可能という。
廃木材の 20〜50% ですと?(バイオエタノールは 15%) これはけっこうおいしいんじゃないでしょうか。なんか発酵じゃないぶんだけ力ずくな感じだけど、この効率の良さは捨てがたい。あとメタノールの利点として、発酵でも作れるし(詳しくは知らないけど)、天然ガスからも作れる(これも詳しくは不明)。こういう、原料をいろいろ選べるってところがエライ。
天然ガスの主成分は メタン らしいから、メタンガスからメタノールを作れるってことかと思われる。日本の周辺海域の底には メタンハイドレートが豊富にある。メタン自体 CO2 発生量が少ない良質な燃料だけど、常温で気体ってのが難点。そこでメタノールにすれば扱いやすくなる。さらにそれをジメチルエーテルにすると、ディーゼルエンジンで使えるようになる(多少の改造が必要らしいけど)。
ていうか調べたらジメチルエーテルの沸点って -23.6℃なんだね。常温で気体か。ちょっと扱いにくそうだな。 LPG(液化プロパンガス)みたいに高圧で液化してくれるんだろか。それだったらまぁなんとか実用で扱えるかなって感じだな。
けど、事前の感触じゃほぼそのまま軽油と置き換えられそうな気がしてたんだけど、燃料タンクの代わりにボンベじゃあなぁ。配管もそれなりに漏れ防止策を講じなきゃいけないし、現行のディーゼルエンジンを積んだ乗り物や土木工事機械との互換性がないってことが分かってしまった以上、ちょっと興醒めな感じ。
インフラ整備するにしても、常温で気体ってのがネックになりそう。確かに自動車用 LPG のインフラはある程度整ってるっつう前例があるから不可能じゃないだろうけど、長距離トラックなんかが途中のガソリンスタンドに寄って燃料を詰めるってほど簡単にはいかなそうな気がする。
つうことで、ディーゼル用の燃料としてはちょっと将来性が不利っぽいかなぁ。燃料電池の原燃料として注目されてもいるみたいだけど、それよりだったら毒性の強さをさっ引いても、常温で液体のメタノールを使ったダイレクトメタノール方式の方が有利な気がする。メタノール自体、ジメチルエーテルより汎用性が高そうだし、製造工程が少ないぶんだけ安く上がりそうだしさ。
って、メタノールそのまんまじゃディーゼル燃料の代わりにはなんないわけで、そこらへんにジレンマを感じますなぁ。
もしエタノールからジメチルエーテルを作れれば、将来的にガソリンスタンドは燃料電池自動車に合わせてエタノールスタンドになりそげなんで、各スタンドで、エタノールを原料にジメチルエーテルを作ってトラックに供給するって体制が取れそうなんだがなぁ。こんな素人考えは通じなさそうですなぁ。つうか、大型車も燃料電池にすればいいんじゃないかと今気がついた。それならスタンドが用意すればいいのは、エタノールだけで済むことになる。それでどうでしょうかね。
いやいや、そもそもディーゼルエンジンが燃料電池に置き換えられるまでコスト的にしばらくかかりそうだから、それまでの間、ジメチルエーテルじゃどうかって話なんだよな。うむむむむむむ。
いや〜今日は振り替え休日だったけど、天気はいいし風もなかったしで、現場で要らない木製品をばんばん焼いたよ。んで焼きながら思ったんだけど、いくら木がバイオマス燃料だからって、30年も40年も前の、地球温暖化が問題になる前に作られた木製品をこの21世紀に燃やすってのは、どー考えても大気中の二酸化炭素(CO2)増加に貢献しちまってるんじゃないかと。
計算してみる。乾燥木材に含まれる可燃物質のうち約 95% が炭素(残り約 5% は水素)。燃えないで灰として残るのが全重量のうち約 5%。てことは 0.95×0.95 で、燃やしたぶんの約 90% が CO2 となって大気中に放出されたわけだ。今日だけで木を推定 400kg くらい燃やしたから、炭素 360kg が二酸化炭素になった。この CO2 換算で3分の11をかけて約1.32トンの排出(炭素原子1個あたりに、酸素原子2個がくっついたぶんだけ質量が増える)。なんか明らかに地球環境に悪いことしちまってるよなぁ(汗)。しかも燃やさにゃいかんものまだまだワンサカある……。
昨日とおととい書いた、廃木材をエタノールやメタノールにしてくれるお便利かつ環境にやさしい工場、近くにまだないもんなぁ……。
| もくじ | ||
 |
||
 |
 |
 |
| 前の月 | ホーム | 次の月 |