これはすごい。映像的に。
この神々しさよ。
物理的には「たまたま逆光でレンズハレーションが起きてるだけ」と言ってしまえばそれまでだけど、この撮影のタイミングでそれが絶妙なアングルで発現してしまった事実というのがね、素直に尊いなと。
素敵な動画を見せていただきました。
ロボジーhttps://ja.wikipedia.org/wiki/地球フライバイ・アノマリー(地球フライバイ以上)
なんか探査機がスイングバイした後に、軌道が計算値と実測値が微妙にズレることがあるらしく。一体何の力がどう働いておるのかという謎ということで。
計算値は事前に算出したものだし、実測値はまさに実際の事後の結果だし。ズレるはずがないのがズレてると。
2012年までは本当に謎で、なんか宇宙論的な何かが作用してるんじゃないのかとかまで言われてたりしたっけ。今はある程度の目星がついてるそうで。
とりあえずパイオニア・アノマリーの方は、搭載してる原子力電池(RTG)からの熱放射が加速を促してたのが2012年に判明。それまでは放熱の合計に方向性がないんであり得ないとされてたのが、よくよく再計算し直したら、合致する答えが出てきたよと。
残るは地球フライバイ・アノマリーだけど、Wikipedia を見ると「なお2006年現在、日本のはやぶさ等に関しての分析は報告されていない」と出てる。記事が書かれたのは2012年以前ですな。
そういうことかな。いやいや「2013年10月9日の木星探査機ジュノーによる地球スイングバイでは、アンダーソンにより近地点前後で 7 mm/s 程度の速度変化をもたらすアノマリーが予測されたため注目されたが、結果は否定的なものであり、……」ともある。いやこの文章、アノマリーが発生しなかったって話だな。
んじゃもう原因は宇宙論的なものじゃなく、探査機自らが発生させるエネルギーによるものってことでいいのかな。あるいは太陽光圧の計算の精度がイマイチだったとか、そういうオチかも。
反古の紙が大量にあるんだわ。これをアルミと歌詞の燃料に利用できんもんかと考えてきたわけでさ。
シュレッダーして廃食用油と混ぜて固めるテンプルするとかも考えたけど、廃油と固めるテンプルだけで塊を作ったらこれがちょっと、ちょっとって感じの出来で。固体燃料として使えるもんじゃなく。だったら固めないで液体のまんまでいいやって感じ。
紙ってそのまんまだとすぐ燃え尽きちゃうし、なんだったら火がついた状態で舞い飛んで危ないし。ペラペラに薄いのがよくない。
じゃあ厚さ数センチのブロック状に仕立て直せれば……と。けどそのやり方がどうにも思いつかない。
シート状のまま洗濯ノリとかに浸して乾かして固めるのも手かな。けど燃えながらペラペラ剥がれて、あっという間になくなってしまいそう。それに、ある程度の密度が欲しいところ。
ジューサーミキサーをしつこくかけて、紙をパルプに近い状態まで持って行って……水分を抜くと、繊維同士が絡まって、ひとかたまりになるにはなるだろうけど、水気を飛ばすとスカスカの穴だらけになりそげ。
人型ロボってかなり昔にイギリスで作られてたんだなー(棒)
これはどう見てもwwwww 取材陣の疑心モロ出しの表情もいいね。
2012年の映画で『ロボジー』というのがあってだな。なんかそれ思い出したwww とりあえず吉高由里子のカワイさがよかったなぁ。
英語の "pure" の日本語訳って、場合によっては「コテコテの」で通じるような気がする。
「純粋な」って訳は、どうも堅苦しくてな。ほぼじゅびふぉ でも時々この訳で悩んでたりする。歌詞を扱うっつう事情から、漢語よりも和語の方がしっくりくる場合が多いし。
「ピューリタン」=「清教徒」なんで、そこから「清い」「清らか」を引っ張ってきたりもする。それでピッタリなときもあったりするし。けどまだカバーし切れてないというか。
「コテコテの」を足しても全部は埋まらなさそうだけど、それなりに埋まるかなと。
やっと峠を越したですよ。
ほぼじゅびふぉの不定期メンテナンス(死んでる動画を探し出す)用のプログラム、一応稼働するまでになったですよ。
やる気あんまし起きないまんま、たぶん丸1年はかかったろうか。もっとかな。ちびっとちびっと進めたり戻ったりで、先月あたりにようやく方向性に当たりがついて、今日もいろいろうまくいかなくて、調べては試して。んで、ようやく試作機が出来たと。
ハリウッド特撮ってもう今はミニチュアなんか使わなくて、デジタルですわな CG ですわな。
そりゃもう CG の完成度って完璧だからな。んでもうそこらへん観客の感覚も飽和してしまって、もうどんなにステキな CG を見ても特に感慨を覚えなくなっちまった。
んでまぁただの懐古趣味だけど、昔のハリウッドのミニチュア特撮って味があったよなと。そこらへんでいうと日本の特撮のことも出てくるんだけど、そこらはもっと好みの話だね。日本の特撮の独特の魅力もたまんない。けどハリウッドとなるともっとリアル寄りに厳しい基準って感じでな。高度でカネかかる技術を湯水の如く注ぎ込んでも、やっぱりちょっとだけ出てしまうミニチュアテイストがね、もうね。
それがよく現れる被写体が蒸気機関車だよなーとか。『バロン』(1988)、『バック・トゥ・ザ・フューチャー Part3』(1990)、『ドラキュラ』(1992年)ですわ。
『バロン』の場合はけっこう露骨にチャチい。つかハリウッド特撮はチャチいビジュアルだとカットを短くして、観客が気づいてしまう前に次のカットに移る手口が一般的。けどこの作品だと日本映画みたいにじっくり見せる。てことでおもっきし模型だとバレちゃう。けどそのチャチさを逆手に取って観客に一杯食わすのが監督テリー・ギリアムだなよと。
『バック・トゥ・ザ・フューチャー Part3』のメイキングを見たら、崖から墜落する機関車は模型だった。いやー本編じゃ気づかなかったですよ。その模型がけっこうデカくて。両手で抱えてやっと持てるかなってくらい。重量的に二人がかりかな。
日本の特撮だと大抵は片手で掴んで持てる感じのサイズ感なんで、やっぱしちゃちい感じがしてしまう。日本だと鉄道は大体同じ縮尺の模型だなーって感じがするんだけど、着ぐるみの怪獣に合わせて「標準」になったのかもな。
で、どのくらいデカいと観客に「実物だ」と思わせられるのか。そうかそのくらいなんだな。
つか以前に上野の科学博物館で「スター・ウォーズ展』を見てきてさ。実際に撮影に使われたミレニアム・ファルコンのミニチュアのサイズが直径 1m くらいはあって、そのデカさにびっくりしたっけ。あの説得力はサイズにあったんだなーと実感したですわ。
『ドラキュラ』の蒸気機関車は背景や照明込みで実物じゃ表現できない系だったんで、敢えてのミニチュア模型ですな。背景込みで作り込んでるんで、機関車のサイズは『バック・トゥ・ザ・フューチャー Part3』よりも小さめかと。けど造りや動きにリアル感が出まくってる。「騙せたと思うてか。バレてんだよ。いやでもこれはこれで……」。この錯覚感がたまんなくイイわけですよ。
CG の完成度の高さを前にしちゃ、もうミニチュア特撮は過去作品で楽しむしかなくなっちまった感じだな。どの業界でもアナログ技術って職人技と職人同士のチームワークだから、仕事が減れば維持できない。けっこう簡単にロストテクノロジーになってしまう。今どきわざわざ独特の味わいのためにミニチュア特撮をやる意味もないんだろうし。
あーでも新作でミニチュア特撮を見たいっつうこの欲求はどうすればいいんですか(無駄な半ギレ)。つか映画全体がデジタル高精細化してしまってるんで、ミニチュア特撮はフィルム時代よりもボロがたくさん出てしまいそうでもあるな……。
ほぼじゅびふぉ のメンテ作業(作品自体が消滅したページを探して消す)を開始。曲目データベースでのコメントアウトが終了。105作品が消滅してたよ。
あとは、該当ページを、ローカルでは「公開終了」フォルダに移して、リモートサーバ上では消去。そして曲目データベースのコメントアウトを削除って流れ。
収蔵作品数が3000も越してしまうと、前みたいに1ページずつ開いて確かめるってのがもうね、って感じで、そこらへんのある程度の自動化を目論んでた。んでこの度ようやく落成したわけでさ。
自動化の概要は、各作品ページの動画窓の HTML コードを抽出して、30個くらい並べたものを1ページにして表示して、ザーッと見ていく形にする。ってのは決まってた。んだけど、いろいろやってみて、失敗しては別なルートを開拓していってさ。
最初は Perl CGI でやろうとしたけど、処理がタイムアウトで失敗。今度は JavaScript メインで行こうと思ってたけど、それだとニコニコ動画の動画窓が出てこないことが判明して失敗。
そこまでで、動画窓 HTML コードを抽出・列挙して書き出す Perl プログラムができてた。こいつを前半として利用すれば、タイムアウト問題はどうにかなりそうってことで、後半は CGI に戻そう、となった。
でさ、事情によりというか、普段の iMac じゃなく、東芝のノート PC で作ったんだわ。けどさ、これに Ubuntu を入れてるんだけどさ、どうもローカルで CGI を動作させる設定がうまくできなくて。んで思いついたのが、書いた CGI プログラムをリモートサーバにアップロードして試す方法。
これが決め手。ようやくできたですよ。これにより、力仕事は手持ちの古くて遅い PC じゃなく、高速・大容量なリモートサーバに肩代わりさせるっつう新発想も得たww
つかこれ大昔からある UNIX のマスター・スレーブ方式ですがな。重たい処理は高性能なリモートサーバにやらせるんで、クライアント側はただの端末としての、しょぼい PC で全然オッケーっつうやつで。
ほぼじゅびふぉ のメンテ作業中。
rockleetist さんのほかに、木のひこさんも引退されとったかー orz
噂話ってのは尾鰭がついて広がるもんでして。ひどいときは大元は何もないのに噂話だけが出たりして。
そんな無責任な話が出ては広まってしまう理由のひとつは、たぶんこのコトワザのせいなんじゃないかと。
「火のない所に煙は立たず」
「そんな噂が出るからには、出どころには絶対何かある」という確信を生む呪文ですな。
いやいや、噂だけ煙だけいきなり経ってしまうってあるじゃないですか。自分のことを周りがヒソヒソ言っててさ、ヒソヒソさんを捕まえて確かめてみると、全然身に覚えのない話だったってのはよくある話で。
物理的にも、立つよ煙。火がなくても。むしろ火がつく前から煙って出るよ。太陽光と虫眼鏡で紙を燃やす時とかさ、板の上でキリ揉みして火を起こす時とかさ(やったことないけど)。そこに気づくと、
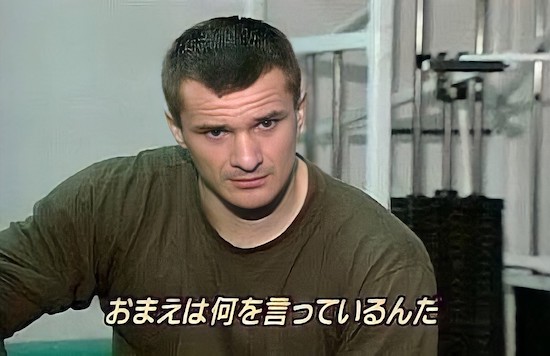
としかなんないわけで。
「コトワザというものは、昔から通用してきたからには世の中の真理を突くものだ。うむそれで間違いない」という気がするもんではあるけど、こういうダメコトワザってのもあるんだなーと思ったり。
前に書いたことあるけども。
「鉄は熱いうちに打て」→ 人間は鉄ではない。また、鉄の鍛造はデタラメにぶっ叩けばいいってもんでもない。
「麦は踏めば強くなる」→ 人間は麦ではない。また、麦踏みはデタラメに踏めばいいってもんでもない。
「獅子は千尋の谷に我が子を落とし、自分で這い上がってきた子のみを育てる」→ そんな動物は実在しない。そもそも千尋の谷とはどこにあるのか。全部嘘っぱちではないのか。
まーここらへん、虐待とかいじめとかする人の言い訳に使われる常套句なんですけどね。
中島みゆきは麦踏みをモチーフにした感動的な歌を作って歌ったけど、あれは踏まれる麦に自らを重ねる内容であって、踏んずける側の屁理屈では決してない。
コトワザも使いようですな。使う立場によってはダメコトワザになり得るってわけで。
昔。たぶん20世紀末あたり、携帯電話が普及しつつある頃。
「携帯電話の電波で脳がチンされる」っつう話があった。「チン」は電子レンジのこと。
なんか携帯電波が発信する電波は電子レンジで使われる電磁波と周波数が近いらしく。耳に当てて通話すると、おもっきし脳をチンされてしまうって理屈で。
そんなわけで当時は、普通の携帯の電波出力の100分の1程度の PHS のほうがいいんじゃないのか、みたいな話があった。
今はもう実質的に PHS が絶滅して20年くらいかな。携帯電話っつうと、いわゆる普通のやつだけになった。
なし崩し風味もある感じだけど、「脳チン」は結局ガセネタだったってことでいいのかな。
「自分に理解できるものは正しい」「自分に理解できないものは間違っている」
そういう判断基準って、気持ちはわかるし、自分も気付けはそれで判断してたりもする。ただ、その判断のしかたがおかしいってのはあるわけで。
けっこうなお歳でも、それに気づいてない人っていたりするんだよな。こういう人とはどうも合わなくて。つか合う人って限られてるかと。けど本人は、自分の感性と合わない人については上記の論理で「相手が間違っている」と結論して、無駄につらく当たったりするわけで。
その判断基準が主観だってのが問題なんだよな。
やっぱし分かり合える日は来なさそう。
日本で見る世界地図って、日本が真ん中に来てるじゃないですか。けど世界標準の世界地図って、ヨーロッパが真ん中なんですわな。日本は右(東)の端。アメリカでも世界標準を使ってて、アメリカ大陸は左(西)の端なんだよな。
日本の世界地図を見て、ヨーロッパの人はツッコミ入れたりしてるみたいだけどさ、いや別に「日本が世界の中心」とか日本人が思ってるわけじゃないんだわな。地図上で日本を中心に据えると、日本人にとっては便利なんですよ。自国から見てそれぞれの国や地域がどの方向にあるのか感覚的にわかりやすいわけで。ただそれだけなんだけど、どうもそれで納得してくれないっぽい。
というのも、ヨーロッパは「自分たちが世界の中心」って意識がいまだに強いらしく。「経度の基準になっているのがイギリスのグリニッジ天文台だから、ヨーロッパを中心にした世界地図が正統」という主張もあるみたいだけど、たぶんこれこじつけ。あくまで「ヨーロッパが世界の中心」っつう意識が強いんだと思う。
日本人には別に世界の中心はヨーロッパとは思ってないし、グリニッジが経度0°だから何? てなもんで、ヨーロッパが地図の左端にあっても別に不都合はないわけで。
日本にとってはぶっちゃけヨーロッパよりもアメリカのほうが存在感がエグいんで、地図上では日本とアメリカが太平洋で繋がってる構図の方がわかりやすい。日本人とっては日本式世界地図の方が実用的なんですわ。
言葉としては、日本があるあたりは「極東」と呼ばれてるわけで。日本人は「ここは極東」なんて特に意識してないけど、ヨーロッパ目線ではそうなんだなってのは理解できてると思う。別にそれでいいじゃないですかと思う。
アメリカはどっちのバージョンの地図でも端っこになっちゃうわな。で、アメリカはヨーロッパ中心版を選んでる。これって歴史的にアメリカがヨーロッパとのつながりが東洋よりも強かったからだと思う。で、アメリカは「自分が世界の中心だ」と言いつつも、世界地図で『でも本当の中心はヨーロッパ』と植えつけられてるわけで。
その意識が、アメリカの比較的なヨーロッパ重視・アジア軽視を生んでるんじゃないかと思う。首都もヨーロッパに面してるし。つか単純に、アメリカの領土から見て、大西洋の対岸と太平洋の対岸って距離が倍くらい違うってのもあるんじゃないかと。
マーティ・フリードマンに言わせると、アメリカのアーティストがワールドツアーで必ず日本を入れるのは、(欧米版の世界地図で)最果てまで行くんだぜっつう印象があるからだそうで。なるほどなー。欧米の地図だとアメリカは左端で、右端の国にまで行くってのは「ワールドツアー」として箔がつくもんな。アーティスト本人たちがそういう気になるのはもちろん、対欧米のマーケティングで説得力ありそうだよな。
実際に欧米の世界地図で北米からもっと遠いのはオーストラリアとニュージーランドだけど、巨大経済圏感とエキゾチック感が強い日本ってインパクト強いんだろうな。最近は中国も入れたりしてたっぽいけど、どっちかっつうと日本での異文化体験と、その体験のポジティブな感想の公開のほうが宣伝効果が強いって感じですか。日本礼讃は最近の世界の流れらしいからな。それにうんざりしてるアンチ層も増えてるみたいだけど、人気が出ればアンチも出るのが世の常だわな。
日本ブームでインバウンド収入に沸く日本としては、海外からどう思われてるのかってのはけっこう大事なわけで。
そこでですな、世界じゃ日本と違って、ヨーロッパ中心の世界地図が標準ってのを覚えておくと、そこらへんの心理をより正確に読む足しになるんじゃないかと。
脈絡もなく思い出した。山形新幹線の開業してしばらくは緊急停止が頻発してたっけな。在来線区間の踏切でトラブルが多かったような。ミニ新幹線の営業は史上初だったからしょうがない。
そんな折、おいらは山形市の中心街でのイベントに参加した。パフォーマンスチームのメンバーとして。前に書いたことあったと思うけど。
なんかイベントのスケジュール埋めみたいなテキトーな企画で、前日にいったん集まって、リーダーが大まかな流れを説明して、あとはみんなでリハーサルしながら肉付けしていこうって感じ。
打ち合わせは大盛り上がりで楽しかったんだけどさ、そのネタのうちのひとつで、メンバーたちが並んでぞろぞろと入場する途中、先頭のやつが「きんきゅーてーし!」と掛け声かけるとみんなでドヤドヤと止まるっつう感じで。
とりあえず司会の人たちにはウケてたけど、お客さんに受けたのかはどうだったっけな。もう全然どうでもいいwwww 誰も覚えてないだろうし。
ちなみに緊急停止ネタ出したのおいらwwwwww
いやもう何十年も忘れてたwww
SLS ロケット、延期に次ぐ延期ののち、今日やっと打ち上げ&成功しましたですなー。おめでとうございます。
そういや2011年あたりにこのロケットの構想が発表されたとき、これはいつまでも完成しない夢物語なんじゃないかと思っとったっけな。
って SLS って アレスV とほぼ同じだよね。アレスV 構想と同時に公表された アレスI はどうなったんだったっけ。確かお亡くなりになった気が……ああやっぱし(合掌)
そういやアレスI、『宇宙兄弟』に出てた気がするが……。やっぱし合掌。
ウクライナへの軍事支援ってアメリカが突出してる感じだね。イギリスもジョンソン首相の頃はイケイケだったけど、彼が首相じゃなくなってからは内政がゴタゴタして、ウクライナ支援の話はあまり聞かなくなってしまった。
でさ、日本も支援してはいるけど、兵装に関しては頑張ってヘルメットや防弾チョッキくらいじゃないですか。それでもウクライナ兵の負傷を減らす役に立ってると思うけど、影が薄いっちゃ薄い感じ。
けどその薄い影の中、たぶん日本は密かに別な軍事支援をしてるんじゃないかと。
内閣府が所有・運用してる情報収集衛星(=偵察衛星)
こいつで得た情報を、たぶん米軍経由でウクライナに提供してるんじゃないかと。あるいは、提供を受けた米軍が、自前の偵察衛星で得た情報と合わせて現状把握に利用して、ウクライナへの作戦提案してるんじゃないかと。
米軍自身も偵察衛星をたくさん保有してるはずだけど、いくらあってもいい感じかと。
日本の情報収集衛星は基本、4機構成。光学2機とレーダー2機。光学は比較的高解像度。レーダーは解像度は光学に劣るけど、当地が曇りでも夜間でも見える。んでこの4機合せて、同じ場所を1日1回以上偵察できる。
しかも予備というか、設計寿命を超えて稼働してる個体もあるから、そのぶんの撮影頻度を稼げてるはず。詳細は機密なんでよくわからんけど。
米軍は日本のと自前のとを合わせた情報をウクライナに提供してそうなような。そして日本も自前の情報収集衛星からのデータを分析して、独自にウクライナを支援してる、かも。けどそれって違憲になる可能性があるから、あくまで極秘。あくまでやってない建前。なんじゃないかと。
仮にこれが本当のことだとして。いつの日か軍事に関する改憲が実現しても、やっぱし2022年時点じゃ違憲っぽい感じなんで、公表されることは永遠にないかもなぁ。アメリカ政府やウクライナ政府に対しても、「このことはどうか内密に」と言いつつの支援になりそげ。忍びの道ですなぁ。
報われない努力。報われない助力。
そうとわかってても、日本はこれをやってる気がしてしょうがない。多分に願望が混じってるけど。
機密の塊の情報収集衛星の他に、日本は JAXA 保有の地球観測衛星を何機か運用してる。これもまた当地のいろんなデータをもたらしてくれるんで、分析結果はウクライナ支援の役に立てると思う。
例えば、地域ごとの温室効果ガス濃度を測定する、いぶき(GOSAT)という衛星があってだな。設計寿命は2014年に迎えてしまったけど、今も稼働中。これでウクライナ国内の、普段よりも二酸化炭素濃度が高い地域を割り出して、どのくらい高いかを定量的に割り出しもして、他のデータと組み合わせるとですな、ロシア軍の動向や意向を読めたりもするんじゃないかと。
あるいは陸域観測衛星 だいち2号(ALOS-2)。こいつは合成開講レーダーを積んでる。要は、情報収集衛星のレーダー型と同じ機能を持ってる。機密は特にないけど、もろに偵察衛星として役に立てる。情報収集衛星コンステレーションの撮影間隔を埋めるのに役立てるだろ。
さらに 水循環変動観測衛星 しずく(GCOM-W1)とか気候変動観測衛星 しきさい(GCOM-C1)なんかは、特定ジャンルの研究に特化した気象観測衛星って感じだけど、ひまわりシリーズと違って地球全域を観測できるわけで。当然ウクライナ全土・ロシア全土も視野に入ってる。
軍事じゃ普通の気象衛星からの情報もまたかなり重宝されるらしいんで、特殊な気象観測をする日本の GCOM シリーズも暗躍してるかもよ。
子供の頃の、当時は画期的に思った発見を思い出したよ。
プラモでさ、第二次大戦中の戦闘機でさ、ゼロ戦か何か。日本軍のやつ。出来上がったら塗装するわけですよ。いったん塗り終わって満足してから、何を思ったか全面コンパウンドがけしてみたんですよ。
完成したところ、すげーかっちょよかった。マジかっちょよかった。磨いてる間は「おれ何やってんだろ」とか思いながらだったのに、まったく予想外に美しかった。
思わぬ上出来に、そのあと何日も何日も、手に取っては様々なアングルからうっとりねっとり眺め回してたとさ。
実機はたぶん、敵から発見されにくいようにツヤ消し塗装してたと思う。けどプラモでツヤツヤにしてみると、フォルムの流麗さが強調されるのな。
その頃は旧日本軍の飛行機プラモしか興味なかったけど、外国の戦闘機もそうなんだろうか。ツヤツヤにするとかっこいいんだろうか。スピットファアとかコルセアとかメッサーシュミット Bf109 とか P-38 ライトニングとか I-16 とか。ソ連の寸詰まりの超カワイイやつはうろ覚えだったけど、今調べてようやく I-16 っう名前だと判明したわ。
戦闘機以外でもだろうか。九七艦攻とか一〇〇式司偵とか富嶽とかスツーカとか B-29 とか。B-29 は実機がツヤツヤだわな。
今風のはどうか。F-15 とか ミグ29とか スホーイ57とか US-2 とか C-2 とか。
妄想が暴走モード。
しかし川崎の C-2 って優美なデザインだけど、

垂直尾翼が全体のバランスと合ってない感が惜しいというか。
T字尾翼だと垂直尾翼がゴツくなりがちってのもあるし、大型機の垂直尾翼は巨大になる傾向があるしで、しょうがないっちゃしょうがないか。
アメリカの SLS ロケットは月の有人探査・開発を目的としてるわけだけど、これはあくまでも当面の目的。本当は、火星有人探査を達成するために開発されてきたわけで。
SLS の打ち上げ能力がバカでっかいのはそのためなんだけど、そのロケットで打ち上げる宇宙船オライオン。これも月に行くのは当面の目的。やっぱしこれも、火星を視野に入れて開発されてる。
でさ、月周回軌道の長期滞在でも、火星への往復旅行でも、問題になるのは宇宙放射線の存在ですな。今の国際宇宙ステーション(ISS)は、ヴァン・アレン帯の内側を周回してるから、ヴァン・アレン帯に、宇宙放射線からある程度守ってもらえてる。けど月・火星ミッションだと、ヴァン・アレン帯が守ってくれるってのはもう期待できない。
てことで、月や火星に行く宇宙船は放射線遮蔽が肝どころのひとつになってる。
いやさ、これさ、宇宙船の周囲に磁場でシールドを作れないもんかと。
宇宙船の前後か左右か上下に磁石を対で置けば磁場が発生するわけで。それでどうにかなるんじゃねとか思ったり。
地磁気って磁力としては大したことないわな。鉄が南極や北極に吸い寄せられるなんてことはなく、方位磁針みたいな超低抵抗なヤジロベエ状態の磁石でようやく有意な反応を示す程度。このくらいなら人工で宇宙船の周囲に結界を張れるような気がする。
とはいえそんな単純なことは、宇宙関係の科学者・技術者なら考えてはいるんじゃないかとも思える。つか ISS で不採用っぽいのが、なんかガラクタアイデアなことを醸し出してるのかも。いやいや ISS の場合はまさに地磁気の中を飛んでるわけで。そこに擬似地磁気を発生させると、干渉しあって、場合によっては打ち消しあったりも。その懸念から採用してないとか? 知らんけど。でも月やそれ以遠の有人宇宙船計画でも、人工磁場の話は聞いたことないな。
地磁気の場合は弱くても両極の距離が長いんで、それだけ厚く敷けてる感じではある。人工じゃそこまで再現できなさそうなのがネックなのかな。
ほぼじゅびふぉ の入荷は1作品。
That Distant Shore (彼方の渚) / Sara Beat
Steven Universe のカバーですな。Sara Beat さん、もともと歌ウマなのに、1作ごとに上手くなっていってるよ。
自分から仕掛けた戦争で、勝ち目がなくなってもやめられないし、終戦までの現実的な筋道を描けてもいない……。
今のロシア、大日本帝国の末期に似てね?
はじめは具体的だったはずの「勝利」の定義はもはや、中枢部でさえ各個人ごとに違う、全体としてはボンヤリな観念論。誰かが納得しても他の人たちは納得しない。そんな漠然とした「勝利」にこだわって戦い続けるのみ。生み続けるのは消耗と損失のみ。
大日本帝国と違うのは、国の最高責任者への信頼と敬意が失墜しつつあって、国内の統制が取れなくなってきたこと。
日本の場合、敗戦後も天皇陛下に寄せる国民からの信頼と敬意は変わらず絶大だったらしいけど、そこらへんはむしろ、今のロシアは第二次大戦末期のイタリアやドイツに似てるのかも。よく知らんけど。
ムッソリーニは、自国民に捕らえられて処刑された。ヒトラーは、この世に自分の居場所がなくなったと悟って自決した。
プーチンはどうなるんだろう。日本のケースはもうなさそうだけど、イタリア・ドイツのケースになると決まったわけてもなく。フィリピンのマルコス大統領のケースか? けど亡命を受け入れてくれる国は……中国かな……。
OMOTENASHI は月着陸できなかったかー。
「オモテナシ」月面着陸を断念 ロケットから分離後、姿勢制御できず - Science Portal
JAXAの無人探査機「オモテナシ」日本初の月面着陸を断念 - sorae
なんか分離のとき、想定した状態で放出されなかった、のかな? どこか引っかかって、変な回転がかかって放出されてしまった、とか? そこらへんどうも原因を特定できるデータを取得できてないっぽいのがまた歯痒いところ。太陽電池を機体の片面だけに装備したのも、設計や製作の単純化を考えてのことだったんだろうけど裏目に出た感じ。
JAXA は OMOTENASHI でなんとか日本初の月面着陸のタイトルをゲットしたかったろうに。来年には日本の民間企業の iSpace 社が HAKUTO-R で日本初の月着陸を狙ってるからな。同時にそれが成功すれば、世界初の民間事業での着陸にもなるってことで、iSpace は相当意気込んでると思われ。
実は既にイスラエルの民間企業が探査機 ベレシート で月着陸を試みたことがあるけど、失敗に終わってる。ちなみにべレシートには生きたクマムシを載せてたらしく。墜落地点付近で生き続けてるんじゃないかと噂されてたりww
クマムシが真空、超高温、超低温、強力な放射線に紫外線っつう環境でも死なずにいられる、と言われてるのは、「乾眠」という状態にある時のこと。乾眠中は死んでるようにしか見えないらしいんで、月面で勝手に歩き回ったり増殖したりすることはなさそう。
で、JAXA としてはメンツを賭けて iSpace の HAKUTO-R に先んじたいはずなわけです。
そもそも JAXA はもっとでっかい月着陸機の SLIM を開発中。けどご多分に漏れず予定が遅れてて。SLIM の場合は開発の遅れというより、他のミッションのゴタゴタに巻き込まれて遅れてしまってる。で、その遅れの間に iSpace の出番が先に回ってしまった形で。
本命のはずの SLIM は、2015年に開発スタート。この時点で、2018年にイプシロンロケットで打ち上げ予定 → 2016年、X線天文衛星 ひとみ が稼働直後に全損 → やり直しで XRISM の開発スタート → 想定外の追加予算を有効に使うため、XRISM を打ち上げる H-IIA ロケットの余裕分で SLIM を相乗りさせることに → 打ち上げは2023年に決定、という流れ。
ちなみに SLIM はこの影響でスペックに余裕を持たせられることになり。イプシロン1機チャーターの打ち上げ能力よりも H-IIA + XRISM の余裕ぶんのほうが大きかった。SLIM は設計変更を受けて、逆噴射エンジンがもともとは1基だったのが2基になった(2025.3.16 追記: その逆噴射エンジンの追加が、実運用時にギリギリのところで SLIM を成功側に「転がす」ことになった。ということを、OMOTENASHI 失敗の時点では誰にも知る由がなかった)
さてさて JAXA の前身のひとつの NASDA(宇宙開発事業団)も、かつて「日本初」のビッグタイトルを民間企業にかっさらわれて苦汁を嘗めたことがあった。
そのタイトルは「日本初の宇宙飛行士」。1980年代前半のうちから、NASDA と NASA による長期にわたる厳しい選抜のうえで、毛利さん、向井さん、土井さんの3人が採用。栄えある最初の日本人飛行士は毛利さん。その人がアメリカのスペースシャトルで宇宙に行くことに決まった。毛利さんがミッションを準備してるさなかの1986年、スペースシャトル・チャレンジャー号爆発事故が発生。安全対策を施したシャトルが再稼働するまで2年半も空いてしまった。
シャトルの運用再開後も、順番があるんですぐに毛利さんの出番というわけにはいかない。NASDA は毛利さんとともに来たるミッションの準備と訓練をこなしつつ、ひたすら待つしかなかった。
日本の世の中はバブル景気の真っ最中。カネが余って余ってしょうがない企業続出。テレビ局の TBS もそのひとつ。それで企画したのが、「自社の社員をソ連のソユーズ宇宙船に乗せて NASDA を出し抜く」。1990年、これが見事にキマッてしまった。
確かに日本初で「認定された」宇宙飛行士は毛利さん、向井さん、土井さんなんだけど、初めて宇宙に行った日本人飛行士は、当時 TBS 社員だった秋山さん、となってしまった。
ちなみに今、一般人がソユーズやアメリカのクルードラゴンの座席を買って宇宙に行っても、その人が属するカテゴリは宇宙飛行士じゃなく「宇宙旅行関係者」となる。けど当時は宇宙旅行関係者カテゴリは存在してなくて、秋山さんはソ連に正式に認定された宇宙飛行士となれた。その資格はロシア共和国になった今でも有効らしい。
その後、1992年に毛利さんのスペースシャトル・エンデバー号でのミッションが無事に完遂。このときも日本中が沸き返ったんだけど、NASDA やマスコミが言う触れ込みがどうも、「日本初のスペースシャトルの宇宙飛行士」とか、なんだか歯切れの悪いものになっててな。
ってまぁおいらは無関係のただの日本人宇宙ファンなんでこんな風に言えちゃうけど、NASDA の中の人たちのこのときの気持ちを察するとね、もうね……。
1994年の H-II ロケット初打ち上げ以来、NASDA や JAXA は日本初や世界初のタイトルをガバガバ獲り続けてる。そして久しぶりの屈辱の予感が、月着陸のタイトル争い。ISAS(宇宙科学研究所)は1990年の ひてん、2007年の かぐや で月周回は達成済みだったけど、着陸はなかなかどうして、先送りに次ぐ先送りでモタモタし続けたんだよな。
ISAS の月探査計画で LUNAR-A ってのがあってだな。2004年に打ち上げて、月周回軌道上から月面に、計測機器を積んだペネトレータ(貫入機)を落としてブッ刺して、機器のバッテリーが生きてる間は周回機経由で、月の地下のデータを地球に送るというものだった。
軟着陸ではないけど、月面で稼働する機械を送り込むという意味で、日本初の月面着陸になるはずだった。けど開発難航がたたって最終的には打ち上げ前に計画は放棄された。
かぐや はもともとは、軌道周回機と着陸機のセットで、1機の H-II または H-IIA ロケットでまとめて打ち上げるはずだった。けど 1998年、1999年と続いた H-II ロケットの連続失敗を受けて、リスク分散の名目で別々に打ち上げることになり。もうその時点で着陸機の運命線がかなりかすれてたけど、やっぱりというか「予算確保が難しい」と着陸機はキャンセルになった。
で、モタモタして月着陸できないでいる JAXA / ISAS は、月より先に、もっと難しい小惑星着陸(と離陸)を、2個の小惑星で2回ずつやってのけたww しかもサンプルリターンまでミッションコンプリートwwww これ世界初と2番目。3番目がアメリカ。こっちは来年に地球にサンプルを届ける予定。宇宙開発の各種技術も予算もあるのに他国が成功済みの華々しい計画の後追いしかしない、あの中国も計画してるっぽい。
同時に SLS から放出された、これまた日本の超小型宇宙機の ECUULEUS は問題なく稼働してるっぽいぞ。
ちょ、ウソだろ? ドイツに勝った? マジか!?
ジ ャ イ ア ン ト キ リ ン グ か よ!!
「盛り上がらない」と言われてた今大会、とりあえず日本じゃ今から大盛り上がりだろうなー。
3年前のラグビーW杯のときと同じく、日本が初戦で金星ゲットした途端ににわかファンになってるおいらですww
んでさ、なんかヨーロッパは開催国のカタールに対して、人権がウンヌンでおもくそ難癖つけてるみたいだけど、そこが理解できないんだが。
スポーツの大会には、政治や思想を持ち込まないのが原則だろ。男子サッカーの大会に、なんで性的少数者の権利がどーたらこーたらの話をねじ込もうとするんだ?
カタールの法律じゃイスラム教に従って、性的少数者は違法扱いらしいね。まーヨーロッパに比べてイスラム圏の意識が遅れてるとか違うとかってさ、よその文化はよその文化ってことで、とりあえず放っとくのがマナーなんじゃないかと思うが。つまり余計なお世話でしかないだろと。
つかお呼ばれした家で、その家に対して文句つけるのはヨーロッパ文化じゃ OK なのか?
で、ドイツ代表チームは試合前、試合のユニフォームで性的少数者の権利を主張する計画を出したら FIFA と主催者に拒否られて、それへの抗議の意味で、試合前のチーム集合写真で全員とも手で口を塞ぐっつう変なパフォーマンスしてたわな。なんかなーこいつらしつけーなーとかドン引きしてたら、狙ったわけじゃないけど日本がぶちのめしましたなwwww
ドイツ様より明らかに格下な日本ごときがやってくれたってのもあって、世界中がそれで盛り上がってるっぽいwwwwww 「政治的主張なんかより先に自分のやることやれよ」とツッコまれまくりwww
ヨユーかましといて負けるってのはかなりかっこ悪いよな。ロンドンオリンピックでのスペイン代表みたいなことになっちまったww あのときは下馬評でスペインが優勝候補でな。「黄金世代」と称されてたチームメンバーも、始まる前から決勝戦がどーたらとか話してた。そしたら予選の1回目で当たった日本にいきなり負けちまって。そのあとはボロボロの乱調でまさかの予選落ち。
今回のドイツもそうなりそげなジンクス発動な感じがしてきたが……。
「粉(こな)」、「紛(まぎ)らわしい」。
同じ漢字だとずっと思ってたwwww
粉 紛らわしいんだよ。
英語の「右」は "right" ですな。けどこれ同じ単語で「正しい」も表しますな。「左」の "left" のもう一つの意味は、「残り」。なんとなく、とりあえず「右」を「正しいほう」として、じゃあ「左」は「そうじゃないほう」してるような。
「インドじゃ左手は不浄なものを扱う手」というのが有名だけど、イスラム教圏でもそうらしい。西洋でも、お辞儀をする時に右手を胸に、左手を背中に、あるいは体から離して手のひらを相手と反対側に、というポーズがある。憶測だけど、たぶん左手は、礼儀を示す相手に対して隠すか遠ざけるという意味があるんじゃないかと。
てなことで英語でも、きっと「右手」は「左手」より「正しいほうの手」だったんじゃないかと。
けど今の西洋じゃ優劣の意味での右手・左手の区別はない感じだわな。お辞儀も、しきたりとしてのただのポーズとして残ってるだけなような。
飛行機の操縦士・副操縦士や管制官との会話は英語だけど、「正しい(同意する)」の意味じゃ "right" という言葉は使わないことにしてるらしい。「右」と紛らわしいんで。てことで、その場合は "correct" を使うのが「正しい」のだそうで。なんかのハリウッド映画でそう言ってたから確実www
あれって「ニキシー管」っていうんだな。画像検索すると、その独特なレトロな美しさがいっぱい並んでて壮観ですなー。
もうどこでも生産してないのを、チェコの個人が復活させたんですな。という記事を見つけた。
柔らかな光で数字を表示する「ニキシー管」ができるまで - GIGAZINE
できるまでの工程があまりにも多い……。てことで単価もお高い。けど現代の液晶や有機 EL と違って、個人の規模で製造できないこともないんだな。だからこそかつては普通に見られたんだろうな。昭和の昔、まだインベーダーゲームもなかった頃、ゲーセンのゲームでニキシー管を使ったのがあったっけな。
当時も今も、やっぱしこの質感は魅せられるわ。
最近海外でも人気鍵出てきてるらしい J-POP。その曲構造的なヒミツはこれなんじゃね?っつう記事をたまたま見つけたですよ。
J-POPのヒット曲に多用される“純情コード進行”とは? 亀田誠治とスキマスイッチが仕掛けを分析 - Real Sound
正直おいらはコード進行はよくわからん。ブルースの3コードくらいなら雰囲気でようやくわかる程度で。
けど J-POP のヒット曲って明らかにもっと複雑なコード進行だなーってのはまぁ薄々と、てなくらいで。
たぶんこういうのって、コードをデタラメに並べただけじゃ曲の体を成さないわけで。そこら辺、うまく流れる並べ方ってのがいくつかあるはずなわけで。その中でもたぶんその定型というか勝ちパターンというがあるはずなわけで。
そのひとつが、今日のお題の「純情コード進行」というやつなんだろうなと。
おいらにわかるのはこの程度なんで、例えばなぜこの形が「純情」なのかとかまったくわからんwww
まーそういう、コード進行には成功請負人的な形式があるんですよ、というのがわかったのが収穫。
防衛関係の監視衛星を監視する思いつき。
というのを思いついた。
おいらが思いつくくらいだから、本職はとっくに思いついてるはず。これができるのはアメリカだけだろうな。すべての人工衛星の軌道を管理してるからな。頼まなくても衛星打ち上げを勝手に察知して、どんな軌道に何個の物体が投入されたかを勝手に速報するからな。NORAD という組織がそれをやってる。
ただ、静止軌道はやたら遠い。静止軌道に入ってから分離するところまで NORAD は観察できてるのかどうか。できてないとすれば、日本でもこの謎衛星プロジェクトができそうなような。
日本でやれそうなら、中国は絶対やってるだろ。
てことで静止軌道より少し高い軌道には、米中のそういう謎の衛星が飛び交ってるんじゃないかと。
くだらないもしも話。
もしも人間が卵生だったら、鶏やウズラのタマゴを食べるのにいささか罪悪感を持ってたろうなぁ。
胎生でよかったですよほんと。
| もくじ | ||
 |
||
 |
 |
 |
| 前の月 | トップ | 次の月 |